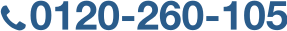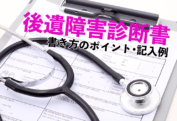交通事故の怪我で治療中、転院する際の注意点

「交通事故後、とりあえずの近く病院で治療を受けているけれど、医師と馬が合わない」
「今の病院は設備が古くて必要な検査をしてくれない」
実は、交通事故後の治療中のこのような悩みはよく起こります。
単に気が合わないだけならまだしも、「治療方針に納得できない」「しっかりと見てくれない・検査を疎かにされる」「病院が家から遠すぎる」などの事情がある場合は、治療の妨げになってしまうこともあります。
このような事情がある場合は、転院を検討すべきときといえるでしょう。
それ以外でも、「通院しているけど症状が改善しない」場合には、転院先を探しはじめるべきといえます。
しかし、途中で医師を変えることでデメリットは生じないのか、転院後に納得いく治療が受けられるのか、保険会社は許してくれるのかなどの不安も多いでしょう。
そこで今回は、交通事故被害者が転院する方法と注意点、メリット・デメリットをまとめました。
1.交通事故の治療中の転院は可能
結論からいって、交通事故被害者が病院を転院することは可能です。
交通事故被害に遭った後は、指定の病院や救急車が向かった病院、行きつけの病院などで治療を受けることになります。
しかし、治療を重ねるたびに、「医師の治療方法に納得ができない」「交通事故の案件に疎いのでは?」と思うことが増えていくケースもあります。
なかなか怪我が治らない場合は尚更です。不信感が募るとストレスも重なっていき、完治までの道のりも長くなってしまいます。
そんなときは、転院先の病院を探しましょう。
交通事故被害者が最初の病院から転院していくことはよくあることですので、安心してください。
「転院すると保険会社から治療費がおりないでは?」と不安になる方も多いですが、きちんと手続きを踏めば転院先でも治療費はおります。
また、医師の治療に問題はないけれど、「家から遠い」といった事情があるケースもあるでしょう。
このように治療に無関係な理由の場合は転院できないのでは?と考える人もいますが、これも心配ありません。基本的に、転院するかどうかは通院している方の自由です。遠くで不便だというケースでも転院は可能です。
このように、交通事故被害の治療中に病院を転院することは可能ですので、不満がある場合はできるだけ早い段階で検討を始めるようにしましょう。
2.転院すべきケース
では、転院をしたほうが良いと考えられるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
(1) 病院に不信感がある
病院に不信感がある場合は早めに転院先を探しましょう。
特に治療方針に納得できない場合は、怪我の治り具合にも関係してきます。ストレスが重なる前に、より良い転院先を探しましょう。
(2) 専門性が足りないと感じる
怪我や症状について難しい問題がある場合、その症状について専門的に取り扱っている病院でないと治療が進まないケースもあります。
治療が難しい怪我・症状であり、担当医や病院が専門医ではない場合は、転院を検討すべきです。
特定の怪我・症状についてより多くの知見を有している病院や医師を探しましょう。
(3) 後遺障害診断書を書いてくれない
治療を進めても完治しない怪我の場合は、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
これを受けることで損害賠償額も増額することができ、その後の生活に不安がある場合でも一定の安心感を得られるはずです。
もっとも、この後遺障害等級認定を受けるためには医師の診断書(後遺障害診断書)が必要不可欠です。
しかし、交通事故被害に詳しくない病院・医師だと、担当医が書き方が分からないなどの理由で後遺障害に関する診断書を書いてくれないことがあります。このような場合は申請ができませんので、転院をおすすめします。
3.良い転院先を見つけるコツ

転院先の病院に不安がある場合にも、しっかりと下調べをした上で転院すれば大丈夫です。
では、良い転院先を見つけるためにはどうすれば良いのでしょうか。
(1) 交通事故の病院について詳しい機関に相談する
良い転院先を見つけるためには、交通事故の病院について詳しい機関や人に相談するのが一番です。
具体的には、後遺障害患者の会・家族会への相談、自動車事故対策機構の療護センターを利用するのが良いでしょう。
これ以外でも、交通事故を多く取り扱う弁護士への相談も考えられます。
交通事故を多く取り扱う法律事務所は、交通事故被害者に協力的な医師・病院を知っていることがあります。紹介を受けることができれば、今よりも良い病院を探すことができるかもしれません。転院について医師や保険会社とトラブルになっても、弁護士ならば対応することができます。
また、紹介先の病院に不安がある場合は、セカンドオピニオンという名目で診察を受けてみるのも有効です。
紹介された病院では一切診察を受けず、そのまま転院される方もいらっしゃいます。ですが、これは自分に合わなかった場合には再度の転院リスクが生じます。
そのため、まずはセカンドオピニオンで診察を受けるのがおすすめです。
治療方針等を聞き、信頼できるかどうかを見極めてから転院手続きを行いましょう。
(2) 病院選択のポイント
では、転院先の病院を選ぶ際のポイントはあるのでしょうか。
治療が難しい症状ではなく、交通事故でよくある怪我・症状である場合は、上述したようにセカンドオピニオンを受けた上、気に入った病院に転院すれば大丈夫でしょう。
しかし、なかなか治療方法が見つからない怪我や症状の場合は、転院先を選ぶのにも注意が必要です。
病院を選択する場合は、①医師の専門性と病院の質、②医師の印象などに気をつけると良いでしょう。
医師の専門性と病院の質
完治が難しい怪我である場合や、症状の改善がなかなか見られない場合には、特定の怪我・症状について専門的な知識を持つ医師の診断を受けるべきです。
例えば、交通事故被害で高次脳機能障害が残ってしまうケースなどでは、専門的な医師による診察が必要です。
そのため、病院として、高次脳機能障害の症状について専門的な治療を行っている病院を探しましょう。
これまでの実績やその怪我について評判をリサーチすることで、より良い転院先をみつけることができるはずです。
また、病院の質も重要です。質というのは、施設が充実しているということです。
後遺障害等級認定を受けるためには、MRIやその他の精密検査を受けることが必要となります。施設として整った環境で治療を受けることにより、小さな異常も見つけてもらいやすくなります。
医師の印象
医師に対する主観的な印象もあながち無視できません。
というのも、実際に話してみると相手の印象や医師の人格などがわかるためです。
良い施設で専門性の高い病院であったとしても、医師が協力的でない限り治療は進みません。そのため、医師に対してどのような印象を持ったのかについては非常に大切です。病院の施設内容や医師の専門性だけでなく、実際に相談した際の印象も大切だということも覚えておいてください。
セカンドオピニオンを受ける際に、信頼できそうか、協力してくれそうかなどもしっかりと見極めることをおすすめします。
4.交通事故被害で転院するメリットとデメリット
(1) 転院するメリット
①今より良い治療が受けられる
転院することの一番のメリットは、より良い治療を受けられるということです。
現在の病院にてなかなか症状が改善しない場合等でも、専門性の高い病院に転院することで改善が見られる可能性があります。
また、これまでの方法とは違う治療を受けられる可能性もあります。
②適切な後遺障害診断書を書いてもらえる
症状が完治しない場合は、一定のところで治療が終了し、症状固定と診断されます。その際、医師に診断書を書いてもらうことになりますが、この診断書は後遺障害等級認定の決め手となる重要なものです。
そのため、内容に不足があると、ご自身の希望する等級が受けられなくなることもあります。
後遺障害等級の認定につき、協力的な病院・医師に診てもらえれば、より適切な診断書を書いてもらえるケースもあります。
診断書の中身がよくなれば、等級認定も希望通りとなる可能性が高くなるのです。
③遠い病院に通わなくて済む
救急車で運ばれた場合、自宅から遠い病院に急送されてしまうこともあります。この場合、入通院で苦労することもあるでしょう。
転院先に、家から近い病院を選べば負担も軽くなります。
ご自身が入院されている場合でも、家族が通いやすい病院を選択することで、家族全員のストレスや負担を軽減することができます。
(2) 転院するデメリット
転院にはメリットだけが存在するわけではなく、一定のデメリット(リスク)も存在します。
①転院先に良い病院・良い医師がいるとは限らない
しっかりとした事前チェックを行っていれば、「医師と合わない」「治療方針に納得いかない」「専門性がない」ということは少ないと思います。
しかし、セカンドオピニオンを受けずに転院を行った場合は、転院先の病院も合わないという事態が想定できます。この場合は再転院も考えなければならず、負担が伴います。
専門性から病院を選んだ場合でも、交通事故対応には詳しくない病院であるケースもあるでしょう。
この場合は不便がでる可能性もあるため、弁護士と連携することで、うまく後遺障害等級認定や示談交渉を進めていく必要があります。
また、しっかりとチェックをした場合でも、「思った以上に良くならない」「他の治療も受けてみたい」というケースもあるため、実際に治療を受けてみると自分には合わなかったという事態も考えられます。
②度重なる転院は示談交渉や後遺障害認定に不利
後遺障害等級認定を受ける際、診断書に納得がいかず転院することもあるでしょう。
この場合、転院前の病院にご自身にとって不利な診断(カルテ)が残ってしまうことになります。
一度の転院であれば問題となることは少ないですが、何度も転院を繰り返していると、不利な記録が積み重なることになります。
この場合は、後遺障害等級認定を受ける際に不利な証拠となってしまうこともあります。
また、示談交渉に影響し、損害賠償の額も変化する可能性があるでしょう。
③転院によりストレスがかかってしまう
転院する際は、多少の転院手続きが必要です。また、慣れた病院から新しい病院に転院する場合には、勝手がわからず不便を感じることもあるかもしれません。
このような場合、怪我や症状の負担と重なり、特に環境の変化に不安を感じやすい方は更なるストレスを感じてしまうかもしれません。
ストレスが増えると治療が長引き、回復が遅れてしまいます。
5.転院の際にすべきこと
転院の際の手続きとしては、
- 病院に対して行う手続き
- 保険会社に対して行う手続き
の2つがあります。
(1) 病院に対して行う手続き
事情説明
まず、今現在の病院の主治医に事情を説明しましょう。
「家が遠いので、近くの病院に転院したい」「専門的な治療を受けるために、別の病院へ転院したい」「治療方針に納得できないので、別の病院に転院したい」などです。
基本的には、きちんと説明すれば医師が転院を認めないことはないでしょう。
主観的な内容である場合には、「ここで治療を続けた方が良い」と説得を受けるかもしれませんが、このような場合でも転院したい旨の意思をしっかりと伝えることで理解を得られるはずです。
紹介状を書いてもらう
事情を説明した後は、転院先への紹介状を書いてもらいます。
診断書の内容として、怪我・症状の内容、治療経過等を記載してもらいます。
書いてもらった後は、ご自身で内容に不足がないか確認してください。
転院先の病院に提出
無事に紹介状を書いてもらえたら、転院先の病院に紹介状を持っていきましょう。
これを持っていくことで後の治療がスムーズに進みます。
(2) 保険会社に対して行う手続き
任意保険会社の了承を得る
転院に関しては、保険会社の了承を得ておく必要があります。というのも、加害者の加入する任意保険会社から治療費を病院に直接支払ってもらっている場合(一括対応)、勝手に転院を行うと治療費を打ち切られてしまう可能性もあるためです。
打ち切りが行われると、再び支給してもらうことは難しくなります。そのため、事前に任意保険会社に連絡し了承を得るようにしましょう。
(3) 転院手続きの注意点
紹介状を書いてくれないケースがある
まず、紹介状を書いてくれない医師もいます。
書いて欲しい旨を伝えても書いてくれない場合は、そのまま転院しましょう。紹介状がなくても転院自体は可能です。
もっとも、事前に保険会社への連絡は忘れずに行いましょう。
診断書に「転院」と書いてもらうこと
また、診断書の内容にも注意が必要です。
転院の際に、間違って「治療中止」や「完治、治癒」と記載されてしまうことがあります。このように書かれてしまうと、保険会社が転院を了承しない可能性もあります。
そのため、診断書に「転院」と記載されているかどうかを確認するようにしてください。間違いがある場合は訂正してもらいましょう。
保険会社が了承しないケース
実は、転院を希望したら、保険会社から「治療費打ち切り」を打診されたというケースもあります。
医師の診断書から判断して、転院を認めないという判断をする保険会社もあるということです。
このような場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
これを押して勝手に転院すると、治療費が打ち切られてしまう可能性が高いので危険です。
6.現在の病院に不満がある場合は転院を
「医師の治療方針に納得できない」「なかなか症状が改善しない」という場合は、できるだけ早めに転院を行いましょう。
転院手続きは、早い方が保険会社の了承も得やすくなるでしょう。
また、交通事故から時間が経過した後に転院する場合は、後遺障害等級認定の際にリスクが生じます。
というのも、転院先の医師は事故後の経過を見ていないため、後遺障害等級認定申請の際に、適切な診断ができない可能性があるからです。
よって、できるだけ早めに転院を行い、治療経過を見てもらうことが大切です。
しかし、「転院先を決めたのに、保険会社が応じてくれない」というケースも少なからずあります。
このような場合は弁護士にご相談ください。弁護士が間に入ることで転院がスムーズに進む可能性もあります。
また、「転院したら治療費を打ち切られてしまった」というケースもあるでしょう。このような場合も、弁護士が交渉を行うことで解決できることがあります。
転院の際にトラブルが生じた場合や、交通事故の示談交渉などについて不安がある場合には、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
より良い病院で治療を続けられ、正当な慰謝料・賠償金を獲得できるよう、親身になってサポートいたします。