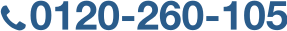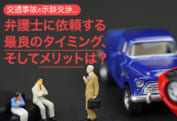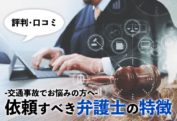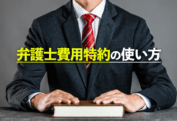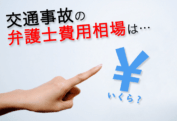道路交通法の目的とは|運転者が注意すべき規定や実際の運用

私達が日常生活を送る上で意識している・いないに関わらず、大きな影響を及ぼしている法律が「道路交通法(道交法)」です。
私達が自動車を運転する、自転車を使う、そして道を歩くときには、道路交通法が関係します。
しかし、私達の多くは、免許が不要な自転車や徒歩の時はもちろん、たとえ自動車免許を取得した後であっても、道路交通法についてあまり詳しくありません。
実際には、道路交通法の各条文において自動車免許の種類・要件、道路標識(追越し禁止、一時停止など)、歩行者の通行方法まで規制されているため、道路交通法を知っておいて損はないでしょう。
この記事では、道路交通法にはどのようなことが書かれているのか?を分かりやすく解説していきます。
1.道路交通法の目的
道路交通法の第1条には、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と書かれています。
【道路交通法の目的】
・道路における危険の防止
・交通の安全と円滑
・道路交通による障害の防止
つまり、誰もが安全かつスムーズに道路を使えるよう、道路交通法にはさまざまなことが定められているのです。
道路の交通に関する決まりについては、かつて道路交通取締法というものがありました。
しかし、戦後の経済発展によって自動車の普及が急速に広まり、交通事故の死亡者数が激増しました。
この状況を打開するために道路交通取締法は廃止され、1960年から道路交通法が制定・施行されました。
道路交通法は、シートベルトやチャイルドシートの着用義務化、運転中の携帯電話(スマホ)の使用禁止、AT車限定免許の導入など、社会情勢等に応じて年々改正を繰り返しています。
また、飲酒運転に対する罰則の強化や、高齢ドライバーへの対応策の制定、自転車の運転に関する規定が改正されるなど、道路交通法はその時代に発生した事件や事故に対応するために更新されていることがわかります。
なお、痛ましい交通事故が発生したときに適用の可否が話題になる「危険運転致死傷」は、道路交通法の規定ではありません。
飲酒運転による重大事故の影響で2001年に「刑法」に新設された「自動車の運転により人を死傷させる行為」に対する刑罰規定が「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」として独立し、危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法の中に規定されるようになりました。
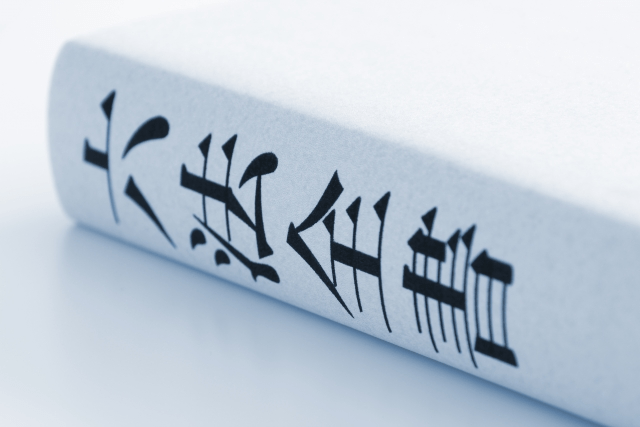
[参考記事]
交通事故と刑法の関係|不安・悩み事は東京の弁護士へご相談を
2.道路交通法が定める内容
以下では、道路交通法の規定内容の代表例を以下にピックアップします。
(1) 歩行者や車両の通行方法
まず、日頃無意識に歩いている歩行者にも、以下のような項目が具体的に定められています。
「歩道等と車道の区別のある道路では、一部の例外を除いて歩道等を通行すること」
「横断歩道がある場所の付近では横断歩道を使うこと」
「斜め横断は一部の例外を除いてしないこと」
車両については、自動車学校などで学ぶことが多いですが、以下のような細かいことまで法律で定められています。
「指定された最高速度を超えてはならない」
「踏切前では一時停止して安全を確認してから通過する」
「急ブレーキをしてはいけない」
「前の車が急停止しても避けられるような車間距離を保つ」
また「停車中の路面電車がある場合は停止または徐行する」など、ケースに応じた内容も具体的に決められています。
(2) 道路の使用
交通の妨害になる、または交通に危険を生じさせるおそれのある道路の使用は禁じられています。
しかし、社会的に価値があるものについては許可を得ることで可能になります。例えば以下のような行為です。
- 道路等の工事
- 石碑、広告板、アーチ、ポストや電話ボックス等の設置
- 場所を移動しないで道路に露店や屋台などを出店する行為
- その他、祭礼やマラソン大会などの行為
(3) 運転者および雇用者などの義務
運転する人に対する義務に加え、社用車などを運転する人を雇っている者が守らなければならない義務も定められています。
飲酒運転(酒気帯び運転)、過労状態での運転、無免許運転の禁止や、安全運転をする義務などについて記載があります。
運転者本人にのみ義務を課すと、雇用者が運転者に無理な運転を強いて大事故に繋がるおそれがあります。
そういった事態を防ぐために、道路交通法では運転者のみならず雇用者側にも義務を設けています。
(4) 運転免許証および講習の基準
運転免許の種類に加え、免許を取得できない人の要件(条件)や運転免許試験などについても道路交通法に定められています。
なお、免許所持者が軽微な違反をすると「違反者講習」を受けるように指示されることがあります。この違反者講習に関する規定も道路交通法に存在します。
また、高齢者に対する講習や、自転車で危険な運転を繰り返した人に対する安全講習などについても定められています。
(5) 反則金制度
駐車違反や速度制限違反などをしたときに支払う反則金についても、道路交通法で定められています。
期日までに反則金を納付することで、違反行為については裁判所に訴訟を提起されなくなります。
逆に言えば、反則金を納めないと裁判所に訴訟を提起される可能性があるということです。
3.意外と知らない道路交通法の定義
ここからは、一般人には意外と知られていない道路交通法の規定・定義、実際の運用をご紹介します。
(1) 制限速度の超過
誤差1割ほど制限速度を超過して運転しても、基本的に取り締まりの対象になりません。
(もちろん、極度に制限速度をオーバーしては取り締まりを受ける可能性があります。)
また、自転車には最高速度の制限がありませんが、下り坂などであまりに高速運転をしている自転車は、危険運転をしているとみなされて取り締まりの対象になる可能性があります。
(2) クラクション・ライトの使用
進路上にいる歩行者等に道を開けさせる目的でクラクションを鳴らすドライバーがいますが、原則的に警笛区域以外でクラクションを鳴らすのは禁止されています。
クラクションは、本来は見通しの効かない場所(警笛区間内)で、自分の存在を他の車に伝えるためにで鳴らすものです。
これに違反すると罰金となりますし、クラクションを鳴らされた人が腹を立ててトラブルに発展する可能性があります。無闇にクラクションを鳴らさないようにしましょう。
例外として、危険を防止するためにやむを得ないときにはクラクションの使用が認められています。
また、ライトについては原則的にはハイビームを使用し、歩行者や対向車とすれ違うときにはロービームに変更します。
ハイビームは「走行用前照灯」、ロービームは「すれ違い用前照灯」という扱いです。
ハイビームのみ、またはロービームのみで運転を続けると違反になります。
(3) 自動車の放置の禁止
以下のような自動車の放置行為は禁止されています。
- エンジンをかけたまま放置
- 鍵をつけたまま放置
- 窓を開けたまま放置
道路交通法では「他人に無断で運転されることがないようにするために必要な措置を講ずる」義務がドライバーに課せされています。
上記の行為はこの義務に違反していることになり、罰則の対象となります。
(4) 高速道路での運転規則
高速道路において、追い越し車線を継続して走るのは違反です。追い越し時のみ追い越し車線を使うようにしましょう。
また、高速道路には最高速度だけでなく最低速度も設定されており、50キロ以下で走行すると罰金の対象になります。
周囲が高速で走行しているなか、低速で走行していると却って危険なのでこういった規定があります。
(5) 水たまり
水たまりなどを走行する際に、水を撒き散らして他者に迷惑かけると違反になります。
水たまりを通過するときは徐行などをして水を跳ね飛ばさないようにしましょう。
例外として、道路に明らかな欠陥があって水を撒き散らした場合には、道路の管理者である行政側に損害賠償を請求できることがあります。
4.まとめ
道路交通法は事故を防止し、安全かつ円滑な交通を実現するための法律です。
自動車を運転するときは、事故を起こさないことはもちろん、道路交通法に代表される各法令を守って安全運転を心がけてください。
しかし、どんなに気をつけても、「信号待ちで停車をしていたら後ろから追突された」「相手から急に突っ込んで来た」とような不慮の事故に遭うことがあります。
万が一交通事故に巻き込まれた場合は、交通事故に詳しい泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士は、ご依頼者様が最良の結果を得られるように相手方保険会社との示談交渉などに全力を尽くします。