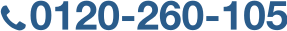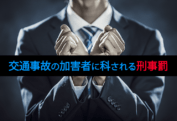交通事故で裁判(訴訟)をする注意点|リスクを回避するには?

交通事故について、ほとんどの案件は示談による解決を図ることができます。
しかし、「相手方損保が思いの外低額の示談金しか提示せず、話し合いが進まない」「どうしても納得いかないので、裁判で示談金を増額したい」というケースもあり得る話です。
ただ、訴訟となると当然時間がかかるだけでなく、裁判費用が生じますし。「裁判に持ち込むことが本当に有効なのかどうか」を検討して決断しなければなりません。
今回は、交通事故案件の訴訟に伴い、注意したり、検討したりしなければならない点をお伝えいたします。
1.交通事故で裁判に移行する前に注意すべき点
(1) 裁判には時間がかかる
裁判になると、多くの場合で判決まで半年〜1年程度かかります。
もちろん、争点が複雑で検討事項が多い場合や、多数の医療機関からカルテや意見書等医学関係の証拠(医証)等を収集する必要がある場合などには、それ以上の期間がかかることも珍しくありません。
半年で終わるのは、多くの場合途中で和解をしたケースです。この場合には比較的早めに終わることになります。
(2) 裁判費用の負担
訴訟をした場合、例え交通事故の被害者であっても裁判費用を加害者側に請求することは難しいと言えます。
また、弁護士費用についても認められることはまずないと思われますが、場合によっては遅延損害金を参考に「調整金」という名目の金額(裁判官が考える妥当な範囲で調整される金額)が付加される可能性もあります。
この調整金が裁判上を起こして和解をするメリットでもありますが、その点のみを見て訴訟を起こすことはリスクが大きいです。
(3) 主張立証責任の多くが被害者側にある
過失について、人身部分の損害賠償請求をする場合には、自賠責法3条によって主張立証責任が加害者側に移ることもあり得ます。
しかし、その他の部分については被害者側に主張立証責任があります。
主張立証責任が被害者側にあることにより、裁判になったら加害者側は損害や因果関係等の重要な部分で厳格な立証を求めてきます。
この立証に失敗すれば、裁判においてその事実はないものとして扱われてしまいます。
(4) 示談交渉段階の金額はリセットされる
また、裁判時点では、示談交渉段階の提示額はご破算(リセット)になります。
訴訟を起こすと、基本的に相手方損保の顧問弁護士が代理人になります。つまり、交渉の窓口が変わることにより、今まで損保側が出してきた額とは全く異なる額を出してくることもあるのです。
このため、しっかり冷静に検討してから訴訟を起こさないと、示談交渉段階の方がまだマシだったという事態になる可能性も0ではありません。
2.訴訟を起こした方が有利になるケースとは
上記のような手間は考えられますが、怪我・後遺障害の内容によっては、訴訟を起こした方が有利になるケースもあります。
(1) 治療経過などについて立証する証拠が十分にある
相手方は、示談交渉段階では実際に通院した治療期間について全期間を認めていても、裁判段階になると手のひらを返して「通院開始から○か月以上の通院について争う」という主張をしてくる可能性があります。これは、特にむち打ちなどの神経症状時には多い主張といえます。
加害者側の狙いとしては、通院期間が減ると医療費について減額できるだけでなく、慰謝料額も減額することができるため、交通事故の裁判上において、この様な主張をしてくるのです。
これに対して、裁判に訴え出た被害者側として対抗する方法としては、「事故によって生じた負傷のために、医学的に必要かつ有効な治療をしていました」と言える状況を作ることが極めて大切です。事故と治療の間に因果関係があることを立証するのです。
治療開始時点からの治療経過について証明する手段としては、医師の診断書やカルテが挙げられます。
このカルテの中に「どの時点で」「どのような症状があり」「どんな治療をして」「どのような回復をたどっていったのか」が分かると、治療の必要性があったと主張しやすいことになります。
医師の診断書をしっかり残せていたら、相手方は争わず、裁判においても一定程度の譲歩をするかもしれません。
一方、むち打ちで整形外科以外(整骨院など)に通院していたの割合が多いような場合には、安易に裁判に訴え出ると、示談段階より低い額になる可能性もあり得ますので注意が必要です。
(2) 特段争いになりにくい後遺障害が絡む事故
自賠責の等級通りに認定されやすい(特段争いのないような)症状で等級認定されたものです。
例えば、可動域制限などについては訴訟提起のリスクも高くないので、検討してみても良いでしょう。
反対に、自賠責の等級表にある類型で非該当等であった場合、一定程度自賠責の判断を尊重することになりますので、訴訟はあまり有効ではない可能性があります。
また、高次脳機能障害などの神経症状については、症状固定時点である後遺障害診断書作成段階より裁判時の方が症状が回復しているようなケースも0ではありません。
このような場合、訴訟を提起することで自賠責の等級から大きく等級が落とされるリスクもあります。訴訟を起こすに際して厳密に検討する必要性があるでしょう
(3) 自賠責の後遺障害等級表から漏れるような怪我がある
新類型の傷病や、類型化があまりされていない怪我の場合には、自賠責の等級が付かないことが多いです。
この場合には、示談による解決に馴染まないといえるので、裁判に打って出る必要性が高いと思われます。
(4) 自賠責等級表通りの労働能力喪失率が妥当でない
例えば、後遺障害認定で14級9号を獲得していたとしても、デスクワークをしている人とスポーツ選手では、稼働可能年数も違えば神経症状による労働能力喪失についての影響も全く違います。
スポーツ選手だと、14級認定のむち打ちでも大きな労働能力の喪失となり得るでしょう。
この様なケースでは、機械的に労働能力喪失率を計算するのは妥当とは言えませんので、裁判に訴える価値があります。
3.まとめ
訴訟になると、主張立証責任の多くが被害者側にあります。示談交渉時点では曖昧で済んだことも、裁判段階においては厳密に主張・立証しなくてはならなくなってしまいます。
このようなリスク・手間がある一方で、訴訟により受け取れる賠償金が増額できる可能性も十分にあります。
もちろん、今回記載した問題以外にも、休業損害や過失割合等、交通事故では争点となりうるものが多数あります。
訴訟を検討する前に、あなたの事例で最もふさわしい解決方法は何か?ということを判断するためにも、一度交通事故事件に強い弁護士に尋ねてみると良いでしょう。