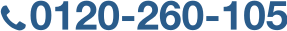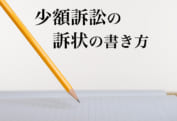交通事故の加害者に科される刑事罰の内容

最近では、交通事故の加害者に対する厳罰化の流れが進んでおり、悪質な交通事故に対しては非常に重い刑事罰が科されるようになっています。
交通事故の被害者が加害者に対する処罰を望む場合、告訴をしたり、被害者参加制度を利用したりすることによって、捜査機関や裁判所に対してその意思を伝えることができます。
被害者の処罰感情が量刑に影響することもあるため、弁護士に相談をしながら、これらの制度の利用を検討しましょう。
この記事では、交通事故の加害者に科される刑事罰の内容や、加害者に対する処罰を求めるために被害者ができることなどについて解説します。
1.交通事故加害者が問われる罪と刑事罰
自動車を運転していて他人を死傷させた場合に成立する犯罪は、現在では「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)において規定されています。
各罪名と刑事罰の内容について見ていきましょう。
(1) 過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」が成立します(自動車運転処罰法5条)。
一般的な人身事故のケースであれば、多くがこの過失運転致死傷罪の適用対象になるでしょう。
過失運転致死傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。
(2) 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、過失運転致死傷罪に該当する過失行為をした者が、さらにアルコールまたは薬物の影響の有無や程度が発覚することを免れる行為を働いた場合には、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が成立します(自動車運転処罰法4条)。
飲酒運転厳罰化の流れから、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪には「12年以下の懲役」という重い法定刑が設定されています。
(3) 危険運転致死傷罪
故意犯とも同視すべき危険な運転によって他人を負傷または死亡させた場合には、「危険運転致死傷罪」が成立します(自動車運転処罰法2条、3条)。
危険運転致死傷罪は2条と3条に類型が分かれており、2条に規定される行為の方がより重大な犯罪として、重い法定刑が設定されています。
危険運転致死傷罪に該当し得る行為は、以下のとおりです。
<2条>
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人または車の通行を妨害する目的で、通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で、高速度で走行中の車に著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速道路などにおいて、車の通行を妨害する目的で、走行中の車に著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行をさせる行為
⑦赤信号などを殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路を走行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
<3条>
①アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、実際にその影響により正常な運転が困難な状態に陥る行為
②一定の病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、実際にその影響により正常な運転が困難な状態に陥る行為
自動車運転処罰法2条に規定される行為により人を負傷させた場合は「15年以下の懲役」、死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」が科されます。
一方、同法3条に規定される行為により人を負傷させた場合の法定刑は「12年以下の懲役」、死亡させた場合の法定刑は「15年以下の懲役」です。
(4) 無免許運転の場合は刑事罰が過重
上記の各犯罪について、加害者が犯罪当時に無免許だった場合には、以下のとおり法定刑が加重されます(自動車運転処罰法6条)。
| 通常時 | 無免許時 | |
|---|---|---|
| 危険運転致死傷罪(2条) | 負傷:15年以下の懲役 死亡:1年以上の有期懲役 |
負傷:6か月以上の有期懲役 死亡:1年以上の有期懲役 |
| 危険運転致死傷罪(3条) | 負傷:12年以下の懲役 死亡:15年以下の懲役 |
負傷:15年以下の懲役 死亡:6か月以上の有期懲役 |
| 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 | 12年以下の懲役 | 15年以下の懲役 |
| 過失運転致死傷 | 7年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 10年以下の懲役 |
交通事故の加害者が犯罪に問われるのは、他人を負傷または死亡させた人身事故のケースのみです。
これに対して物損しか発生していない場合には、過失犯を処罰する法律上の規定が存在しないため、犯罪は成立しません(民事上の責任は発生します)。
2.加害者に対する刑事処分の流れ
交通事故で被害者が負傷または死亡した場合には、加害者に対する刑事処分に向けた手続きが開始します。
以下では、その流れについて見ていきましょう。
(1) 逮捕・起訴前勾留(または在宅捜査)
交通事故の結果が深刻なものである場合には、加害者による罪証隠滅や逃亡のおそれを防ぐために、「逮捕」による身柄拘束が行われます。
逮捕の期間は最大72時間ですが、その後検察官の請求が裁判官に認められた場合には、最大20日間の「起訴前勾留」に切り替えられて身柄拘束が続きます。
その間に、捜査機関による捜査の結果を踏まえて、検察官が加害者を起訴するかどうかの検討・判断を行うことになります。
一方、被害者の負傷が軽微である場合や、加害者に罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断される場合については、逮捕をせずに在宅での捜査が行われることもあります。
(2) 起訴・略式起訴・不起訴の決定
起訴前勾留が終わった段階で、検察官は以下の3つの中から、加害者の処分を決定します。
①起訴(公訴提起)
加害者が刑事処分相当であると判断する場合には、起訴(公訴提起)を行い、公判の場で罪を問うことになります。
この場合、起訴前勾留は自動的に「起訴後勾留」に切り替わり、引き続き身柄拘束が行われます。
起訴後勾留の期間は2か月ですが、必要があれば1か月ごとに何度でも更新することが可能です(刑事訴訟法60条2項)。
なお、起訴された後の被告人については、保釈保証金を預け入れることと引き換えに身柄拘束から解放される「保釈」が認められることもあります(同法89条、90条)。
②略式起訴
100万円以下の罰金または科料に相当すると判断する場合には、加害者の同意があることを前提として、略式手続きによって刑事罰を課すという選択肢もあります(刑事訴訟法461条)。
この場合、罰金または科料の略式手続が完了した時点で、加害者はその時点で身柄拘束から解放されます。その後、罰金などを払わなければ労役場留置となるので、必ず支払いましょう。
③不起訴
検察官が、今回は刑事処分を課す必要がないと判断した場合には、加害者を不起訴処分とすることになります。
不起訴処分は、証拠不十分により犯罪の立証が困難な場合だけでなく、犯罪が明らかに成立する場合にも、情状などを考慮したうえで行われることがあります(起訴猶予処分)。
交通事故のケースでは、以下のような事情が考慮されて、起訴猶予処分が行われるケースが多くなっています。
- 被害者の負傷が軽微である
- 被害者との示談が成立している
- 加害者本人が反省している
- すでに加害者が社会的制裁を受けている など
加害者が不起訴になると、刑事手続きは終了し、加害者は身柄拘束から解放されます。
(3) 公判・判決
加害者が正式に起訴された場合には、公判手続きへと移行し、犯罪の成否や量刑が法定の場で争われることになります。
公判では、検察官が被告人(加害者)の犯罪事実を証拠により立証したうえで、求刑を行います。
被告人側は、犯罪事実を争う場合には、検察官立証に対する反論を行います。
これに対して、犯罪事実を争わずに量刑のみを争うというケースも多く、その場合は被告人に有利な情状を立証することで、寛大な刑を求めるという流れになるでしょう。
審理が熟した段階で、裁判所により被告人に対して判決が言い渡されます。
判決に対して不満がある場合、検察官・被告人の双方には控訴をする権利がありますが、どちらからも控訴が行われなかった場合には、判決日の翌日から14日間が経過した時点で判決が確定します。
(4) 刑の執行または執行猶予
判決が確定したら、実際に刑の執行が行われます。
懲役刑であれば被告人が刑務所に収監され、罰金刑であれば罰金の納付が行われます。
なお、刑の内容が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」である場合には、情状によって、1年以上5年以下の執行猶予が付されることがあります(刑法25条1項)。
この場合には、執行猶予期間中に被告人が再度罪を犯さない限り、刑の執行が猶予されます。
3.被害者が加害者に対して処罰を望む場合にできること
交通事故の被害者が、加害者に対する処罰を望む場合には、以下の対応を取ることが可能です。
(1) 刑事告訴をする
告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪被害を申告し、加害者の処罰を求めることをいいます。
被害者からの告訴があった場合、捜査機関は告訴調書を作成したうえで、一定の捜査を尽くす義務を負います(刑事訴訟法241条2項、242条)。
そのため、被害者からの告訴は、加害者検挙に向けた後押しとして働く可能性があるのです。
(2) 捜査機関に対して厳罰を望む旨を伝える
裁判所が被告人の量刑を判断するに当たっては、被害者がどの程度の処罰感情を持っているかということを、情状の一要素として考慮します。
たとえば捜査機関に対して、被害者として加害者に厳罰を望む旨の書簡を提出しておけば、公判における証拠として検察官から裁判所に提出され、被告人の量刑を重くする方向の事情として考慮されるでしょう。
(3) 被害者参加制度を利用する
交通事故のケースでは、被害者の意思を刑事手続きに反映させるため、公判手続きへの被害者参加が認められています(刑事訴訟法316条の33)。
被害者参加人には、公判期日に出席したうえで、以下のような権利が認められています。
- 検察官に対して意見を述べる
- 証人に対して情状に関する尋問をする
- 被告人に対して質問をする
- 事実関係や法律の適用について意見を陳述する など
裁判官や裁判員も、公判で述べられた被害者参加人の意見をある程度参考にして量刑などを決定しますので、積極的に被害者参加制度を利用して意見を陳述することをおすすめいたします。
4.不起訴や略式処分となった場合の示談交渉への影響
被害者が加害者に対して厳罰を求めているにもかかわらず、検察官の判断により、不起訴または略式起訴の処分が行われてしまうこともあります。
刑事手続きと並行して示談交渉が進められていた場合、不起訴処分や略式起訴処分が示談交渉に影響することはあるのでしょうか。
この点、示談交渉は民事上の損害賠償に関する問題ですので、刑事処分とは独立した問題であるといえます。
そのため、刑事処分の内容が示談交渉に対して影響を及ぼすことは、基本的にはありません。
ただし、嫌疑不十分で不起訴処分となった場合には、たとえば、そのことを拠り所として、過失割合の争いなどにおいて、加害者側が強硬な態度で示談交渉に臨んでくる可能性はあります。
その場合には、民事賠償の観点から改めてきちんと反論する必要があるでしょう。
5.まとめ
交通事故の加害者に対する刑事罰は、近年悲惨な事故が多発していることなどを受けて、年々厳罰化の流れを辿っています。
被害者の方が加害者に対して厳罰を求める場合には、捜査機関と随時コミュニケーションを取りつつ、被害者参加制度を利用するなどして意見を発信しましょう。
なお、加害者側との示談交渉に際しては、弁護士がサポート可能です。お困りの方は、ぜひ一度当所の無料相談をご利用ください。