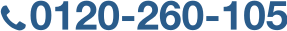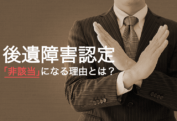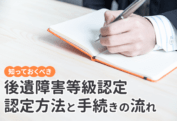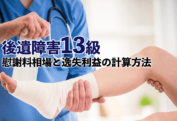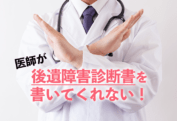後遺症と後遺障害の違いとは?|弁護士が分かりやすく解説

「後遺症」という言い方は一般用語としてよく用いられている言葉ですが、交通事故被害の損害賠償の文脈では、加害者の保険会社は「後遺障害」という言葉を使います。
交通事故における「後遺症」と「後遺障害」という2つの言葉は、似ているようで明確に異なる意味が存在します。
この記事では、この違いについて解説いたします。
1.後遺症と後遺障害の違い
(1) 後遺症とは
後遺症とは、病気や怪我など急性期症状が治癒した後も、機能障害などの症状や傷痕が残ることをいいます。
例えば、「自動車追突で頸椎損傷を起こし外科治療で治療したものの、その影響で低髄液圧症候群脳脊髄液減少症になりめまいが続く」という交通事故に起因する後遺症のほか、「脳卒中で倒れたあと生涯を通して半身不随になってしまう」というような後遺症もあります。
つまり、交通事故やその他事故・事件などにより受傷してしまった精神的・肉体的な傷害について、病院での治療を続けた結果、これ以上は今後の治療によってもその症状が良くも悪くもならないであろうと医師に判断されたあとに残る傷害が「後遺症」です。
(医師により後遺症が残ったという判断を受けることを「症状固定」といいます。)
他にも「後遺症」は広く一般用語として使われているので、比喩表現として「大地震の後遺症でトラウマが続く」など、物事や事件の後に続く悪影響についても派生して使われます。
(2) 後遺障害とは
後遺障害は、自動車損害賠償保障法(通称:自賠責法)という法律に規定された概念です。
交通事故の文脈においては、一般用語である「後遺症」と法律上の用語である「後遺障害」は違います。
交通事故の「後遺障害」は、大まかに示すと、自賠責法の定めにより以下の2つの要件の両方を満たした症状であるといえます。
①労働能力の喪失を伴う症状
自賠責法は、交通事故の影響で労働能力の低下・喪失をした被害者の逸失利益を救済しようという趣旨も有しています。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたであろう収入・利益のことです。
そのため、自賠責法は症状ごとに、事故がなければ有したであろう能力を100として低下喪失のレベルを分け、それに応じた損害賠償金額を定めています。
たとえば、100/100は常に要介護となった労働能力ゼロの状態ですので、自賠責賠償金では最高額の賠償金4000万円が払われるとされています。
後遺障害は、まずこのような労働能力の低下・喪失を伴うレベルの症状があることが必要です。
②自賠責基準の等級に該当する症状
自賠責保証は、後遺障害の症状の重症度に応じて1級から14級までの等級を定めています。
昇順で番号が若いほど症状が重篤であり、高い損害賠償金額が支払われるという認定結果となります(1級>14級)。
後遺障害の等級認定を行っているのは、自賠責事務所という審査機関です。
自賠責事務所は、加害者の任意保険会社や被害者本人から提出された書類を審査して、いずれかの等級に該当するか(該当するのであればどの等級であるか)を決定をします。
この等級に当てはまらないような症状は、後遺障害とは言えません。
2.後遺障害等級を獲得するためのポイント
後遺障害等級が認定されると、交通事故によって負った怪我そのものに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)に加えて、後遺障害について後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の支払を受けることができます。
そのため、被害者としては、ご自身に残ってしまった「後遺症」が「後遺障害」に該当すると認定してもらいたいところです。
後遺症が後遺障害であると認定されるために必要なポイントを、以下にまとめます。
(1) 交通事故が原因の肉体的・精神的傷害であると証明する
まず、後遺障害の認定を受けるには、対象となる症状が交通事故が直接的な原因である肉体的・精神的障害であると認められる必要があります。
具体的には、交通事故とは関係ない既往症などによるものではないという証明が必要になります。
たとえば、元々ひざに既往症がある被害者の方が、交通事故の被害でさらにひざを痛めてしまい後遺症が残った場合、交通事故の衝撃が引き金になった部分はどこからどこまでか?ということが審査されることになります。
また、むち打ち症などの後遺症によりめまいや微熱が続く場合、これが他の被害者の持病のせいではなく、交通事故の衝撃による神経障害であることを立証していかなければいけません。
交通事故と本人が感じる後遺症状には因果関係が必要なのです(原因と結果の間に理論的な結びつきがある範囲が賠償されます)。
これを証明するためにも、必要な検査をしっかり受ける必要があるでしょう。
(2) 後遺障害診断書の内容をよく確認する
後遺障害等級認定申請をするためには、主治医に後遺障害診断書などを作成してもらい、それを自賠責事務所に提出することになります。
後遺障害診断書を作成してもらえるのは、症状がこれ以上変化しないとして症状固定が行われ、後遺症の病状が確定してからになります。
後遺障害診断書の内容・書き方については、等級認定を受けるためのポイントがあります。
下記のコラムで詳しく解説しています。
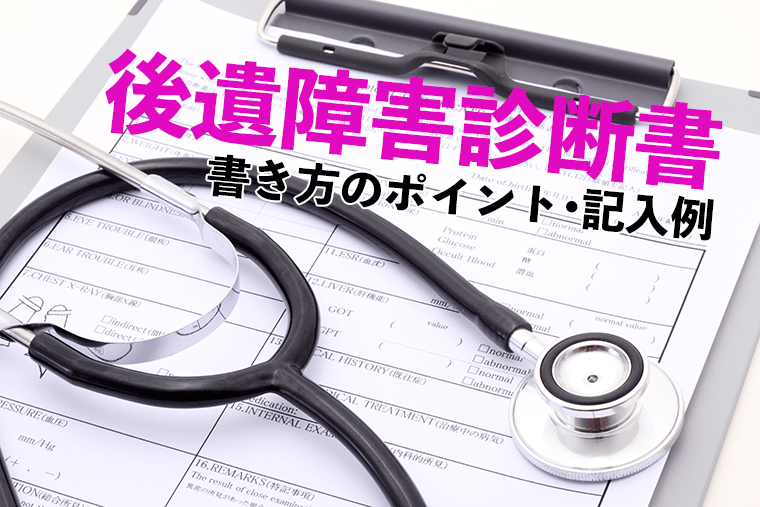
[参考記事]
交通事故の後遺障害診断書|書き方のポイント・記入例
(3) 本人が感じる後遺症状の原因が医学的に証明・説明可能
自賠責事務所による後遺障害等級認定は、書面審査によってのみ行われます。
そのため、本人が感じる後遺症状の原因を医学的に書面で説明・証明していくことが必要になります。
最もわかりやすく説得力のある資料の例としては、骨折や一部損傷など他覚症状です。レントゲンやMRIなどの画像データは特に有効でしょう。一見して原因が証明できるので、自賠責事務所もぶれがなく判断していくことができます。
一方、工夫が必要になるのはむちうち症などの神経症状で、自覚症状はあるけれど画像に映る他覚症状がない場合です。
この場合、画像データなどは準備できないので、医師のカルテ、診断書類、検査結果などの証拠資料を綿密に準備していく必要があります。
むちうち症を証明していくことができる医学的検査としては、以下のようなものがあります。
- ジャクソンテスト
- スパーリングテスト
- 腱反射テスト
- 筋電図
医師は治療のプロですが、損賠賠償金のための後遺障害等級認定について必ずしも詳しいとは限りませんので、医師からこれらのテストを提案してくれるとは限りません。
医師に事情を話し説得力のある資料準備を誠心誠意お願いするとともに、これらのテストを受けたいなどの提案も積極的にしていきましょう。
3.等級認定が下りない場合の対策
後遺障害の対象とならなかったり(非該当)、想定していた等級よりも低い等級認定がされて不本意な思いをされている被害者の方もいらっしゃると思います。
このように、後遺障害認定の結果に不服がある場合、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てが認められれば、認定結果が覆る可能性があります。
異議申し立てを行う場合には、初回申請の際に「なぜ非該当だったのか」「何故低い等級に認定されたのか」などを分析した上で、不足部分について病院や医者に医療照会などを行い、異議申し立てに必要な医証を収集しなければなりません。
また、被害者に残存する症状が認定基準を満たしていることを主張するためには、医師の意見書や新たな後遺障害診断書などを添付しなければならないでしょう。
不服の原因を分析、解明し、認定基準を満たすだけの新たな証拠を提示することには専門的な要素が非常に多くなります。
さらに医療関係者との交渉も必要となるため、専門家である弁護士に相談し委任することをお勧めします。

[参考記事]
後遺障害認定の異議申し立てとは?
4.後遺障害認定手続きは弁護士に相談
上述の通り、後遺障害認定手続きは非常に煩雑で専門知識を要するところですので、認定手続きの準備から請求まで、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが合理的です。
さらに、等級認定された後にはいよいよ後遺障害慰謝料を請求していくことになりますが、後遺障害慰謝料は3つの基準(①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準)のいずれかで算出されます。
3つの中で弁護士基準がもっとも高い慰謝料額を算出できますが、これは弁護士が相手方と交渉しなければ認められることのない算定方法です。よって、賠償金請求も弁護士にお任せした方が示談金が大幅にアップする可能性があります。
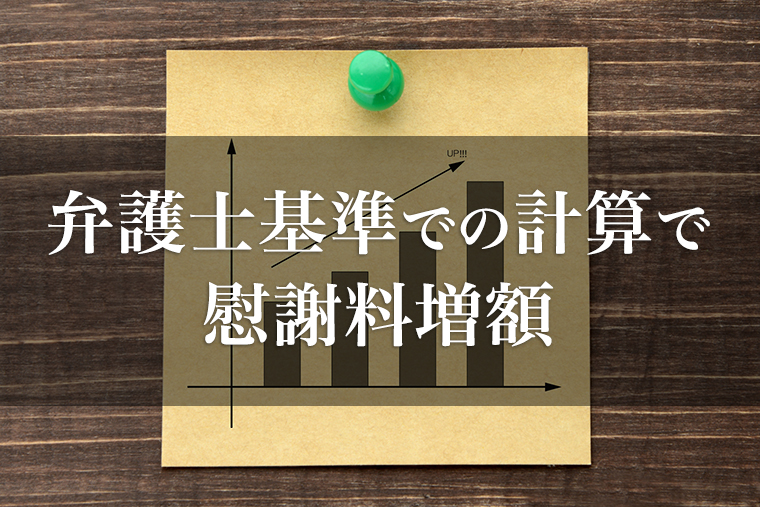
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
泉総合法律事務所にご相談いただければ、交通事故に実績のある弁護士が最後までサポートさせていただきます。