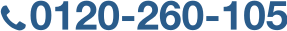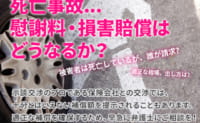後遺障害を負った子どもの慰謝料|大人の後遺障害との違いはある?

子どもが交通事故に遭ってしまったとき、親や家族の悲しみや辛さは計り知れません。治療をしても治らない「後遺症」が残ってしまったらなおさらです。
お金をもらって元の状態に戻るわけではなくても、せめて十分な補償を受けなければ親としては納得がいかないのが当然でしょう。
ここでは、交通事故で後遺障害を負ってしまった子どもについて、親はどれだけの慰謝料を請求できるのか?大人が慰謝料請求した時と金額の違いはあるのか?等を説明します。
1.後遺障害慰謝料とは?
交通事故に遭って怪我をした後、治療を続けても完治せず後遺症が残ることがあります。
後遺症が残ったときには、これが「後遺障害」の基準を満たすと認められることで、「傷害についての賠償金(治療費、休業損害、傷害慰謝料など)」とは別に、「後遺障害についての賠償金」も加害者に請求することができます。後遺障害には1級〜14級までの等級があり、等級別に認定される仕組み(1級の方が症状が重く、賠償金も増額する)になっています。
後遺障害についての賠償金とは、主に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」になります。
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことです。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったという精神的苦痛を金銭によって補償するものです。
後遺障害慰謝料は、等級ごとに算定基準が定められており、その基準をもとに算定します。
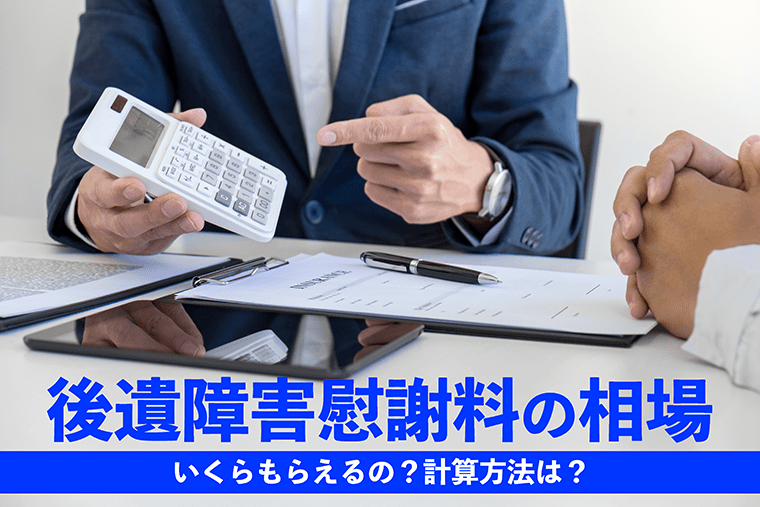
[参考記事]
交通事故の後遺障害慰謝料の相場はいくら?
一方の逸失利益とは、「後遺障害にならなかったら得られたであろう利益」のことで、慰謝料とは違い財産的損害に対する賠償金になります。
事故で仕事を休んだことにより既に発生している収入減少分については、傷害についての賠償金として「休業損害」という形で補償を受けられます。
そして、後遺障害に認定されると、後遺障害についての賠償金としてまだ発生していない将来の収入減少分を逸失利益という形で支払ってもらうことができるのです。
2.子どもと大人で後遺障害慰謝料は違う?
(1) 後遺障害慰謝料では年齢は考慮されない
後遺障害の等級別慰謝料算定基準では、被害者の年齢は考慮されていません。
裁判になった場合でも、被害者の年齢を考慮して慰謝料が算定されるケースは少なくなっています。
現在の算定基準では、後遺障害慰謝料は人によって金額が変わるものではないと考えられています。
交通事故に遭って同程度の後遺障害を負った場合には、基本的に誰もが同じ慰謝料になるでしょう。
逆に言えば、子どもだから慰謝料を増額するという扱いも、通常はされないことになります。
(2) 年齢によって変わるのは逸失利益
後遺障害についての賠償金のうち、被害者の年齢により金額が変わるのは逸失利益になります。
若年者ほど後遺障害により働けなくなる期間が長くなり、逸失利益は大きると考えられるからです。
過去には、まだ働ける年齢ではない子どもの逸失利益は、算定が難しいという理由で、請求できないものとされていました。
しかし、昭和39年に最高裁が子どもの逸失利益も算定すべきという判決を出したため、現在は子どもであっても18歳から67歳までの49年間について、平均賃金をもとに逸失利益を算定するのが基本となっています。
3.子どもの後遺障害慰謝料を増額する方法
このように、後遺障害慰謝料というのは子どもだから高額になるわけではありません。
しかし、大人と子どもの慰謝料が同じというと、納得がいかない親御様も多いのではないかと思います。どうにかして子どもの後遺障害慰謝料をアップできないか、考えていきます。
(1) 弁護士に依頼をする
子どもの後遺障害慰謝料を増額したいなら、弁護士に依頼するのが最もおすすめの方法です。
弁護士は、慰謝料の3つの基準の中で最も高額である弁護士基準に基づき慰謝料請求を行います。
後遺障害慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)という3つの基準が存在しています。
自賠責基準は自賠責で補償される最低額、任意保険基準は任意保険会社の社内基準額、弁護士基準は裁判上でも運用されている基準額で、弁護士基準が3つの基準の中で最も高額になっています。
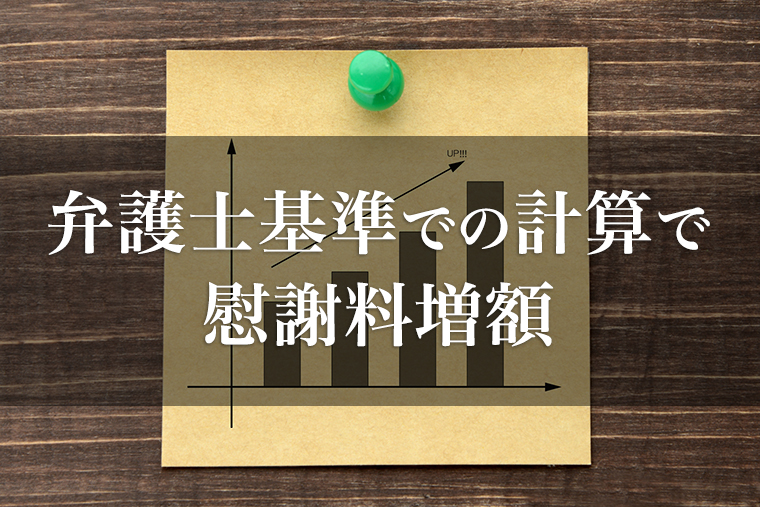
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
さらに、被害者が子どもの場合、弁護士は「後遺障害期間が長いこと」や「将来できないことが増えてしまったこと」を理由に加害者側と慰謝料増額の交渉を行います。
(2) 後遺障害期間が長いことを理由に慰謝料を増額
後遺障害を負ってから亡くなるまでの期間は、老人よりも子どもの方が長くなります。
子どもの方が後遺障害の期間が長い分、当然精神的苦痛も大きいと考えることができます。
そこで、弁護士が交通事故の示談や裁判を行うときには、子どもについては後遺障害期間が長いということを考慮し、大人よりも多めの額を請求することがあります。
東京都にある3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)でも、被害者が20歳未満の場合、後遺障害慰謝料を通常の30%増額すべきと提案しています。
今後は、年齢を考慮した後遺障害慰謝料算定基準に改められる可能性もあります。
(3) 将来できないことを理由に慰謝料を増額
将来できたはずのことができなくなったことを理由に慰謝料を増額できる可能性もあります。
たとえば、後遺障害になったせいで就ける職業が限られることになれば、職業選択の自由が狭められたことを理由に慰謝料を増額できることがあります。
その他に、後遺障害のために行きたい学校に行けないなど、学業に影響が出ることもあるでしょう。結婚や出産が叶わなくなることもあります。そうでなくても、日常生活上大きな不利益を受けることがあるはずです。
将来の可能性を事故によって奪われてしまった子どもの悲しみは計り知れないものです。
大人と同じ通常の慰謝料で妥協するのではなく、できる限り慰謝料増額を目指すべきでしょう。
4.重症・死亡事故の場合に両親が受け取れる慰謝料
交通事故により精神的苦痛を味わうのは被害者本人ですから、被害者本人に対する慰謝料が発生するのは当然です。
しかし、子どもが被害者である場合、本人だけでなく両親の精神的苦痛も相当なものです。
そのため、両親には両親固有の慰謝料を認めるべきではないかという問題があります。
(1) 死亡事故
民法711条には、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められています。
「他人の生命を侵害した」というのは「他人を死亡させた」ということです。
このように、死亡事故の場合には、民法上も被害者の父母に固有の慰謝料が認められることが明らかになっています。
なお、交通事故で子どもが死亡した場合、子どもの慰謝料請求権が親に相続されるという考え方もあります。
この考え方によっても、親は加害者に対し慰謝料請求をすることができます。
(2) 重度の後遺障害
子どもが後遺障害を負った場合には、親が固有の慰謝料を請求できる旨の規定はありません。
しかし、最高裁判例では、「死亡にも比肩しうべき精神的苦痛」を受けたときには、親も固有の慰謝料が認められるとされています(最高裁昭和33年8月5日判決)。
子どもが死亡に匹敵するような重度の後遺障害を負うことになった場合、子どもは当然慰謝料請求できますが、親は親で固有の慰謝料を請求できます。
裁判においては、子どもが後遺障害等級1~5級に認定された場合、親固有の慰謝料請求が認められる傾向にあります。
5.まとめ
お子様が交通事故で後遺障害を負ってしまった場合、弁護士に相談することで最大限の補償を受けることが可能になります。
弁護士は、示談が成立しない場合に裁判までの対応が可能ですから、慰謝料額が大きく増える可能性があるのです。
泉総合法律事務所では、お子様とご両親のお気持ちに寄り添いながら、後遺障害慰謝料増額のために全力で加害者側と交渉します。
交通事故の被害に遭ってお悩みの方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。