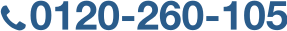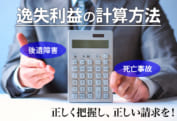子どもにも逸失利益は存在するのか?|正当な慰謝料・賠償金の計算方法
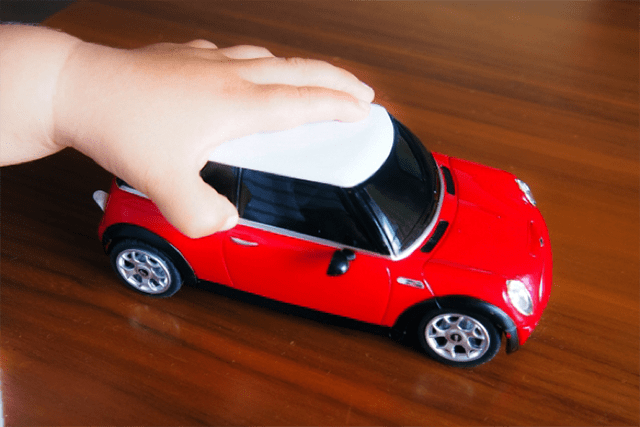
子どもが交通事故に遭いけがをすると、その苦痛に耐えることだけでも大変なことでしょう。まして後遺障害が残った場合には、将来への不安がご家族にも重くのしかかります。
子どもの将来の生活のために適正な補償を受けるには、「逸失利益」を賠償請求することが必要です。
逸失利益とは「交通事故に遭わなければ得られたはずの利益や収入」のことで、示談交渉でも争点になりやすい補償の一つです。
今回は、幼児や小・中学生などの子どもが事故に遭ってしまった場合の逸失利益を請求する方法とポイント・注意点についてご説明します。
1.子どもの「逸失利益」とは?
交通事故による後遺障害が残った場合、損害賠償として、慰謝料のほかに「後遺障害逸失利益」を相手方に請求することができます。
「逸失利益」とは、交通事故による後遺障害を負ったことで失われた収入や利益のことです。
後遺障害によって仕事に就くことができない、あるいは就業できる職種や業務が制限されてしまうなどのハンディキャップを負い、収入の一部または全部が減額されてしまうことへの補償です。
本来大人であれば、逸失利益は事故前の収入をもとに後遺障害の程度に応じて計算されます。
一般的に人が働ける年齢の上限を67歳と仮定し、事故(症状固定)時からの年数と後遺障害の程度に応じて損失がはじき出されるのです。
しかし、将来のことですから確実な収入額を計算できるはずはありません。あくまでも将来的な仮説に立って損失を前払いしてもらうという考え方ですから、これは被害者が子どもであっても同じことです。
2.逸失利益の計算方法
(1) 大人の逸失利益計算方法
通常、逸失利益は下記の計算式に基づいて算出されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数=逸失利益
- 基礎収入…事故前の現実の収入額のことです。
- 労働能力喪失率…行為障害のために将来の労働能力がどのくらい低下したかをパーセントで示したもので、後遺障害等級に応じた比率が定められています。
- 労働能力喪失期間…労働可能上限年齢を67歳とし、症状固定時年齢から67歳までの期間を指します。
- ライプニッツ係数…将来の長期的損害がまとめて支払われるため、労働能力喪失期間分の利息を差し引く必要があります。その調整のための中間利息控除係数です。
(2) 子どもの逸失利益の計算方法
被害者が子どもの場合に問題になるのが、基礎収入と労働能力喪失期間です。
原則として、18歳未満の子どもは修正された計算式を用いることになります。
賃金センサスの平均賃金×労働能力喪失率×(67歳までの係数―18歳までの係数)=18歳未満の逸失利益
- 基礎収入額は賃金センサスの平均賃金額とします。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年公表している賃金構造基本統計調査という統計を基にした平均賃金のことです。 - 労働能力喪失期間は67歳から18歳を引いた49年間とします。
- ライプニッツ係数は、以下の差を係数として用います。
「症状固定時の年齢から67歳までの係数」-「症状固定時の年齢から18歳までの係数」
3.子どもの逸失利益の修正内容
(1) 子どもの基礎収入
収入のない子どもの基礎収入は、賃金センサスの平均賃金を用いて決められます。
子どもの場合、将来の職業を予測することは困難なため、学歴、企業規模などすべての項目の平均値が用いられます。なお、賃金センサスの平均賃金は毎年更新され、年々上昇しています。
賃金センサス男女別平均賃金
賃金センサスでは男女で平均賃金が異なっており、女子の方が低く設定されています。
よって、全年齢平均賃金を用いた場合に、女子は男子よりもかなり低い額で逸失利益が算定されることになります。
令和4年(2022年)賃金センサス(年収)によると、全年齢男女の平均額が4,965,700円に対し、男性は5,549,100円、女性は3,943,500円です。男女間で160万円もの年収格差があるため、結果、逸失利益に大きな開きが出ることになります。
このような性差による格差という不公平さを是正しようとする動きもあります。
東京高裁平成13年8月20日判決は、女子年少者(11歳)の逸失利益の算定について、高裁判決として初めて全労働者平均賃金を基礎収入としました(判時1757号38頁)。
現在の裁判例では、男女格差が生ずることはやむを得ないとする見解がある一方で、幼い子どもの損害賠償という価値判断の問題に男女差が生ずるのは不当だとする見解も増えつつあります。
賃金センサス地域格差
裁判例でも、これまでは年少者の逸失利益について様々な算定方式がとられてきたため、訴え出る裁判所によって金額が大きく異なる事態を招いてきました。このような差異を縮めるため、「三庁共同提言」(※)が発表され、地域格差のない一貫性ある逸失利益の計算を目指しています。
共同提言の骨子は、幼児、生徒、学生の逸失利益の算定において原則、全年齢平均賃金又は学歴平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合に基礎収入を全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金を基本とするというものです。
また、中間利息控除はライプニッツ係数を用いることにしています。
(※3)「三庁共同提言」は、交通事故による逸失利益の算定において最も重要な「基礎収入の認定」と「中間利息の控除」の方法について東京・大阪・名古屋各地裁の民事交通部が同一方式を採用すると合意したものです。全国の地方裁判所における逸失利益の算定は、現在この「共同提言」の内容に沿って行われています。
4.子どもの労働能力喪失期間
子どもの働ける年数については、18歳から67歳までの49年を原則としています。
高校生のなかにはアルバイトをしている場合もあるでしょうが、18歳以下の就労可能年数については18歳から働くという前提になっているのです。
また、後遺障害の残る年数についても、そもそも後遺障害は治らないことが前提ですから、通常は一生涯として考えられ、高校を卒業する18歳から67歳までの49年とすべきと考えられています。
この場合のライプニッツ係数の算出は、「67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数」で求められます。
例えば、事故時10歳の子どもの場合、10歳から67歳までの57年間のライプニッツ係数は18.7605、10歳から18歳までの8年間のライプニッツ係数は6.4632です。
18歳未満の逸失利益の計算には、(67歳までの係数)18.7605―(18歳までの係数)6.4632=12.2973を用いることになります。
ただし、比較的軽度で一定期間経過すれば機能回復が見込まれる後遺障害の場合は、労働能力喪失期間を制限されるケースがあるため注意が必要です。
5.まとめ
交通事故による逸失利益は、将来の収入が減ることへの損害です。被害者が幼児や小さな子どもであっても同様ですから、損害賠償請求することができます。
逸失利益を請求する場合には、弁護士にご相談ください。ご家族が安心できるように、できるだけ被害者に有利になる交渉をいたします。
泉総合法律事務所にご相談いただければ、交通事故に特化した弁護士が情報を徹底的に収集、分析し、交渉にあたります。