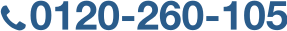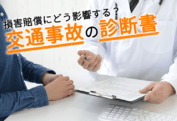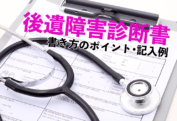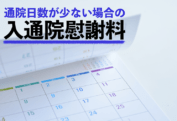交通事故で子どもが重傷を負った場合に家族がするべきこと

幼いお子さんが交通事故で重傷を負ってしまった場合、心痛しないご家族はいらっしゃらないでしょう。
しかし、お子さんの将来を考える上で気を付けなければならないのは、目の前の怪我の治療のことだけではありません。日々の過ごし方についても気を付けるべき点があります。
また、治療を安心して進める上で事故の賠償や慰謝料請求が重要になりますが、それらの充実を図るためにも気を付けるべき点があります。
子どもの交通事故にまつわる基本的な知識と、お子さんのためにご家族がなすべきことを、この記事で確認していただければ幸いです。
1.子どもの後遺障害認定
(1) PTSDなどでは家族による観察が重要
交通事故で受けた将来回復が見込めない精神的・肉体的な後遺症で、自賠責保険が定める「等級」に当てはまると認定されたものを「後遺障害」といいます。
後遺障害はその内容と程度に応じて14段階の等級に分類され、等級に応じて「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」という損害賠償請求が認められます。
後遺障害の症状には、植物状態となってしまったもの、失明したもの、腕や足を失ったものなどのように客観的に明確に判断できるものが多いですが、それらばかりではありません。
神経が麻痺して動かしにくくなってしまう症状や、あるいは命に危険が及ぶ重大な傷害を受けた後に精神的に正常でない反応を示すPTSD(Post Traumatic Stress Disorder 「心的外傷後ストレス障害」)などもあります。
特にPTSDは、日ごろの態度、性格、日常行動の変化が生じます。これらの変化は生活を共にする家族でなければ気づくことができません。
身体の傷が治癒したとしても、その後、お子さんに事故前と違った行動(気力がない、不安がる、落ち着きがないなど)が生じたときは、事故によるPTSDを疑い、継続的に医師の診察を受けることが大切です。
なお、PTSDの症状は多様ですが、主に次のようなものです。
(「後遺障害等級認定と裁判実務」弁護士高橋真人編著、新日本法規発行164頁以下)
【PTSDの症状例】
- 持続する抑うつ状態(悲しい、寂しい、憂鬱、楽しくないなど)
- 不安感、恐怖感が継続する
- 意欲の低下、無関心、自発性、積極性の欠如など
- 幻覚や妄想
- 記憶力や知力の低下
- 衝動的な行動をする、落ち着きがなくなる
PTSDの後遺障害認定(9級、12級、14級)で問題となるのは、被害者の症状と交通事故との因果関係を認めることができるかという点です。
裁判実務では(症状の内容にもよりますが)、「①事故後まもなくの時期から症状が連続していること」「②(交通事故以外に)他の有力な発症原因が存在しないこと」が、因果関係の判定における注目点であると報告されています。
(2) 子どもの逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう将来の利益を金銭的に評価したものです。後遺障害が残ると働いて稼ぐ力(労働能力)も多少なり失われることになりますので、その分将来的に手に入ったはずの金銭が手に入らなくなったと認めてもらうことで、後遺障害の等級に応じた賠償を求めることができます。
未成年の子どもの場合でも、18歳から67歳までの49年間について、平均賃金を元に逸失利益を算定するのが基本です。
後遺障害の正しい認定においては、医師の診断書が重要です。現に生じている障害と事故との因果関係を、診断書によって証明する必要があるのです。
そのためにも、病院にしっかりと通院するとともに、診断書の作成にも気を配らなければなりません。
2.子どもの慰謝料
お子さんが負った怪我については、加害者に対して慰謝料請求が可能です。慰謝料とは「精神的損害」のことです。
慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
(1) 入通院慰謝料
入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも呼ばれます。怪我に対する肉体的苦痛だけでなく、治療・検査のための入院・通院によって費やした時間や手間、不便さなどに対する精神的苦痛に対する慰謝料です。
心情的には、小さな子どもが入通院や手術の苦痛を受けることは、大人よりも可哀想であり慰謝料を増額してあげたいとも思うでしょう。
しかし、入通院慰謝料の算定方法は子どもと大人で同じであり、子どもであることは慰謝料を増額する要素とは理解されていません。むしろ、子どもは回復力が高く治癒が早いので、入通院期間が大人よりも短く、期間を基準とする入通院慰謝料が安くなる傾向があるようです。
また、回復が進むに従い、通学や友人と遊ぶことを優先して、通院がおざなりになるケースも珍しくありません。これも入通院慰謝料が安くなってしまう要因です。
通院期間・頻度は入通院慰謝料の算定に反映しますし、何よりもしっかりと怪我を治すことが子どものためです。症状が無くなるまでしっかりと治療を受けさせることが適正な慰謝料請求にも繋がります。そのため、通院はしっかりさせることが重要です。
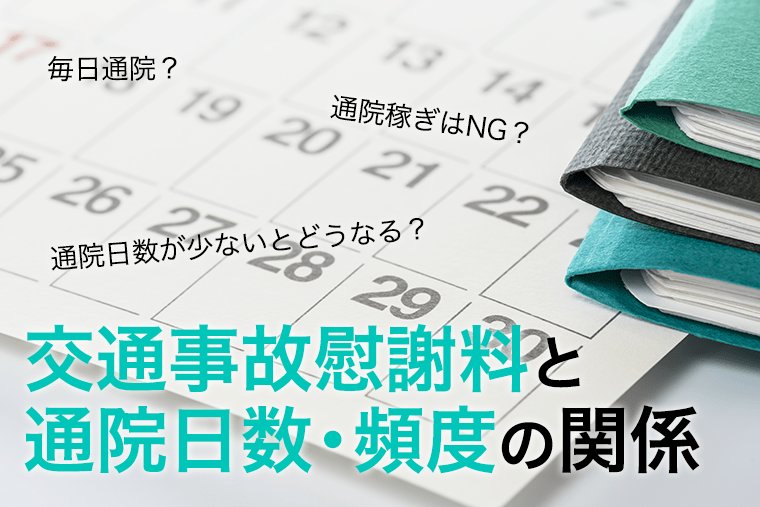
[参考記事]
交通事故のリハビリは毎日通院?|慰謝料と通院日数・頻度の関係
(2) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったこと自体に対する慰謝料です。後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
大人よりも子どものほうが事故後の将来が長く、後遺障害から受ける影響が大きいため、子どもの後遺障害慰謝料は大人の場合よりも増額するべきではないかという議論があります。
たしかに、後遺症で苦しむ年数は、子どものほうが長いです。しかし、年数を慰謝料額に反映させてしまうと、「5歳の子どもと15歳の子どもの後遺障害慰謝料に10年分の差をつけるべきか?」という問題も生じるため、若年者に対して後遺障害慰謝料を増額するという扱いはされていません。
一方で、余命の長い子どもの場合、後遺障害逸失利益の金額が非常に多くなります。実務的な感覚ではそれでカバーできていると見ているのかもしれません。
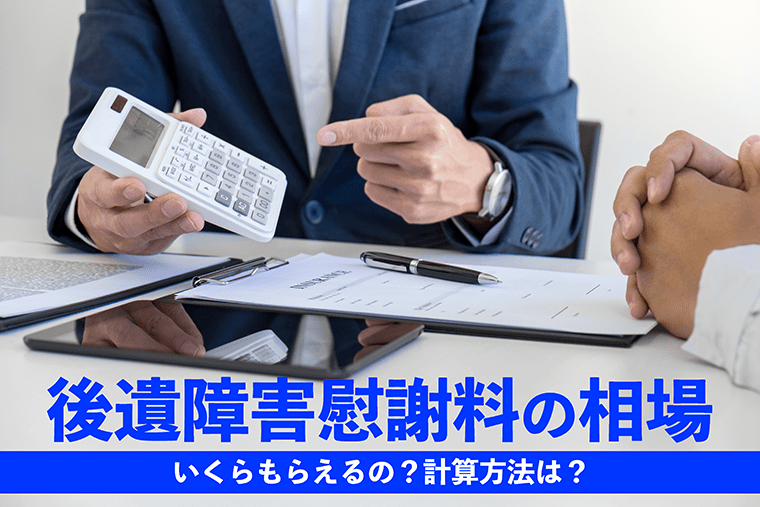
[参考記事]
交通事故の後遺障害慰謝料の相場はいくら?
3.子どもの過失相殺
事故発生時の過失に応じて交通事故の損害を当事者が分担して負担する割合を「過失割合」と言います。
スピード違反や前方不注意など、被害者にも何らかの過失があるときは、被害者が受け取る賠償額を減額することが公平です。
そこで、損害賠償額を定める時には被害者側の過失を考慮しなければなりません。これが「過失相殺」です。
(1) 幼い子どもに過失相殺は認められない
子どもが交通事故に遭った場合、それが2〜3歳の幼児であれば、たとえ道路に突然飛び出したケースであっても、「被害者の過失だから」と相殺することはできません。
そのような幼児には、物事を判断する能力がなく、過失相殺を認めることはかえって不公平だからです。
逆に、被害者に事理弁識能力、つまり物事の道理をわきまえる程度の判断能力があれば、過失相殺が問題となります。
具体的には、5〜6歳程度のお子さんになると、事理弁識能力が裁判上認められることが多くなり、過失相殺の問題となる可能性が出てきます。
(2) 過失相殺問題に関して家族が出来ること
大人であれば、「どういう事故だったか」「事故当初に何が起こっていたのか」について自分の言葉で説明することもできますが、小さいお子さんではそれはかなり難しいことになります。大きな怪我をするようなショッキングな事故であればなおさらです。
そのため、過失相殺などの問題になりそうな場合、お子さんに代わってご家族が事故の態様を代弁できるように、状況をしっかり把握しておくことが大切です。
4.子どもの交通事故も泉総合法律事務所に相談を
子どもが被害者となった交通事故について色々と注意すべき点を記載しましたが、「具体的にどうすれば良いか分からない」「子どものために頑張りたいが、しっかりと対処できるか不安だ」ということもあるかと思います。
現実にこうした問題に直面し、お悩みのことがあれば、交通事故対応の専門家である弁護士に相談しましょう。
泉総合法律事務所にご相談いただければ、交通事故について経験と実績の豊富な弁護士がご相談者様の状況に応じて的確にアドバイスさせていただきます。
何がご心配な点・ご不明点があればあわせてお伺いしますので、お気軽にご連絡ください。