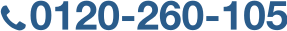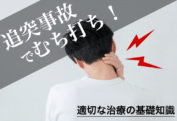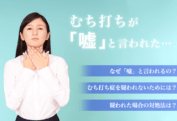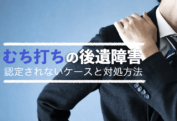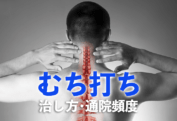MRIで「異常なし」ならむち打ちの通院は打ち切りになる?
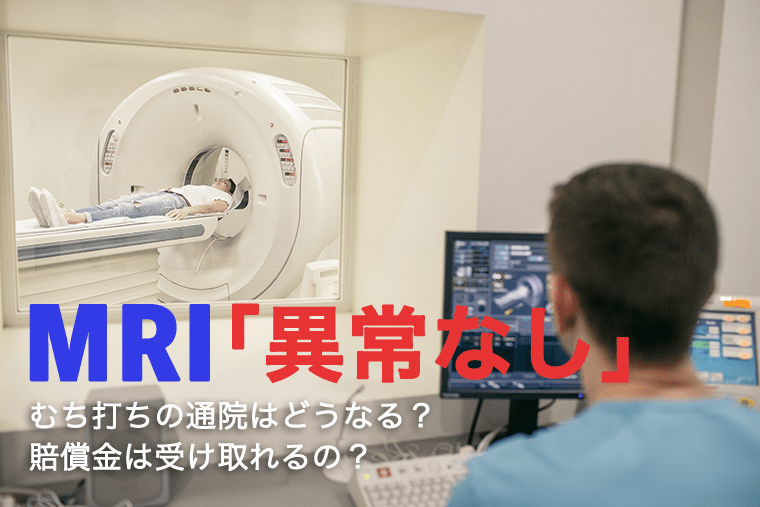
追突事故の被害者が発症し易い「むち打ち」では、レントゲンやCTでは分からなかった異常がMRIによって発見できることがあります。
しかし、そのMRIでさえ「異常なし」という所見が出てしまうこともあります。
こうなると、相手方保険会社に「異常がないなら治療費は打ち切りで」と言われてしまうことがあります。
果たして、MRIで異常なしと言われたら、痛みがあっても治療費を打ち切られてしまうのでしょうか?また、後遺障害認定を受けることはできないのでしょうか?
今回は、むち打ちのMRI検査が「異常なし」と診断された場合の交通事故被害者の対処法について解説します。
1.MRIの検査結果が異常なしとなる理由
前述した通り、レントゲンやCTではわからないむち打ちの異常が、MRIであれば発見できることがあります。
レントゲンやCTが、X線を被験者に照射して透過させることで体内の状態を確認するのに対して、MRIは、磁気によって体内の状態を確認することで、レントゲンやCTでは見つけ難い軟部組織や神経組織の異常を発見できるからです。
しかし、むち打ちでは、しびれなどの症状があっても器質的損傷(体の組織の損傷)を伴わないことがあるため、神経症状の原因がレントゲンやCT、MRIといった画像検査で確認できないことも多いのが実情です。
こうなると、保険会社からむち打ち自体を疑われ、損害賠償の金額などで被害者が不利に扱われてしまうリスクが生じます。
2.MRIで異常なしと診断された場合
では、MRIで異常なしと診断された場合には、交通事故被害者にはどのような影響(デメリット)があるのでしょうか?
(1) 治療費打ち切りの可能性
MRIの診断結果が異常なしとなれば、保険会社から、「それなら、これ以上治療の必要はありませんね」などと治療費の打ち切りを打診されてしまう可能性があります。
(むち打ちの場合は、ただでさえ、一般的に治療期間の基準とされる3ヶ月を超えると保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性があります。)
しかし、症状の診断については医師がするものです。安易に保険会社の言い分に応諾してはいけません。
保険会社に言われたからといって必ず治療をやめなければならないわけではないので、まだ痛みやしびれがあるならば我慢せず、医師に治療の継続を訴えてみましょう。
保険会社から治療費打ち切りを打診された場合の対処法について、詳しくは下記のコラムに譲りますが、保険会社への対応が不安なら、弁護士に相談してみてください。
弁護士へ依頼をすれば、保険会社への対応以外にも、下で説明する後遺障害等級認定のアドバイスを受けられる、慰謝料増額の可能性が期待できるといったメリットがあります。

[参考記事]
むち打ちで「治療打ち切り」を告げられた時の対処法
(2) 期待した後遺障害等級の認定が受けられないおそれ
むち打ちで認定される可能性がある主な後遺障害には、次の2つの等級があります。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 実務上の判断基準 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
|---|---|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚的所見により医学的に証明可能である | 290万円 |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 症状が医学的に証明可能である | 110万円 |
12級13号については、MRIなどの客観的所見で、事故から生じたといえる外傷性のヘルニア等、むち打ちの原因を医学的に証明できなければなりません。かなりハードルが高いと言えるでしょう。
対して、14級9号については、症状に一貫性・連続性が認められ、自覚症状と神経学的所見が一致する場合に認定される可能性があります。
MRIで異常なしという所見であっても、その他の神経学的所見があれば、むち打ちの後遺障害等級認定が受けられる可能性はあります。
ただし、12級と14級とでは後遺障害慰謝料の額に100万円以上の差がついてしまい、認定で非該当となれば後遺障害慰謝料を受け取ることができません。MRIで異常なしと出たならば、後遺障害に関する賠償金が思ったよりも低額になってしまうおそれがあります。
特に、外傷性のヘルニアなど所見があるといえる際には、後遺障害認定の申請前に慎重に再検査をしておくべきでしょう。

[参考記事]
むち打ちの後遺障害認定|12級・14級の違い
3.MRIで異常なしと診断されたときの対処法
では、むち打ちがMRIの診断で異常なしという結果になった場合は、どうすればいいのでしょうか?
(1) 通院は継続し、主治医に自覚症状を訴える
後遺障害等級認定には、通院期間と通院頻度が大きく関係します。MRIで異常なしという所見であっても、諦めず、症状固定するまで通院を続けましょう。
また病院では、主治医に、自分の症状の一貫性・連続性を診断書に正確に記録してもらい、後遺障害等級認定に備えましょう。
(2) より強い磁力のMRIでの再検査
MRIは、磁力によって解像度が異なり、現在、0.5テスラから1.5テスラが主流となっていますが、3テスラのMRIを導入している病院も存在します。
もし、MRIで異常なしという所見に納得できない場合には、より強い磁力のMRIで再検査を行えば、異常が発見される可能性があります。
(3) セカンドオピニオンを求める
MRIで異常なしとされても、患者が症状を訴えていれば、直ちに医師が治療を終了するとことはまずないでしょう。仮に保険会社からの治療費が打ち切られても、医師の判断さえあれば一旦は健康保険を使い治療を継続することができます(治療費は後から保険会社に請求します)。
しかし、もし、主治医が保険会社の言い分通りに症状固定を通告した場合は、他の医師にセカンドオピニオンを求めるといった対応も必要になります。
セカンドオピニオンを求めた医師が、治療の継続を勧めれば、その医師のもとで補償を受けながら治療の継続が可能になります。
4.むち打ちではいつMRIを受けるべきか
正当な損害賠償金を受けるためには、怪我について正しいタイミングで正しい検査を受けることが重要です。
最後に、人身事故でむち打ちになってしまった場合にMRIを受けるべきタイミングを解説します。
(1) 事故から比較的近いところで病院でMRIを受ける
むち打ちは、受傷後2~3日経過してから症状が現れることもあります。もし、事故後むち打ちの症状が現れたら、すぐに病院で整形外科を受診してください。
事故後しばらくしてからむち打ちの原因を特定できたとしても、保険会社から事故との因果関係が疑われてしまい、交通事故以外の原因でむち打ちになったのでは、と言われかねません。
通常、交通事故で受診をするとレントゲンの撮影が行われますが、前述した通り、むち打ちのケースはレントゲンでは原因が特定できない可能性があります。
むち打ちが疑われるときは、極力早くMRI検査も受けてください。事故後すぐのMRI検査でむち打ちの所見が認められれば、損害賠償請求の強い証拠となり得ます。
なお、むち打ちの症状について詳しくは、次のコラムをお読みください。

[参考記事]
追突事故でむち打ち!対応のポイントと慰謝料相場を解説
(2) 症状固定時にもう一度MRIを受ける
むち打ちで症状固定となりそうなら、もう一度MRIを受けましょう。
症状固定とは、それ以上治療を継続しても症状が改善しない状態を指します。症状固定となれば、その後は後遺障害等級認定を受け、後遺障害慰謝料の請求をすることになります。
後遺障害等級認定では、MRIのように症状を客観的に証明できる画像所見があるとより可能性が上がります。
後遺障害等級認定の資料とするためのMRIを受けておけば、後遺障害の認定確率が上がる可能性があるでしょう。
5.まとめ
MRIの診断結果が異常なしであっても、保険会社からの治療費打ち切りの打診への対応はもとより、保険会社への損害賠償請求は可能です。
一般に難しいと言われるむち打ちの後遺障害等級認定でも、泉総合法律事務所では、ご相談にいらした被害者にMRIを受けていただき、異議申立てをした結果、非該当から14級の等級の認定を受けた実績もあります。
MRIで異常なしという診断結果でも諦めてしまわずに、是非、当事務所へ一度ご相談ください。