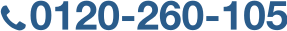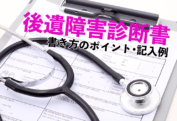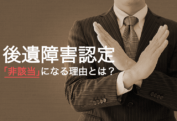肋骨、骨盤の骨折による後遺症|症状と認定基準・慰謝料

交通事故で胸部に損傷を受けたときには、肋骨骨折となることが少なくありません。
また、歩行者対車両の事故で歩行者が尻もちを付いたケースや、骨盤周辺に追突されたときには、骨盤を骨折することがあります。
特に骨盤骨折は、股関節や骨盤周辺の内臓にも影響を与えることがあり、重篤な症状(後遺症)が残ってしまうこともあります。
この記事では、交通事故で肋骨、骨盤を骨折したときの症状や、加害者に請求できる慰謝料について解説します。
1.肋骨骨折、骨盤骨折の症状と後遺症
(1) 肋骨骨折
肋骨(ろっこつ)は、「あばら骨」と呼ばれることもあり、胸部内臓を覆う細い骨です。内臓を外傷から保護する役割を果たしていて、脊椎から内臓を取り囲むように付いています。
肋骨は細長い骨であるため、骨折しやすい骨として知られています。机にぶつけた程度の衝撃や、高齢の方などでは咳をしただけでも肋骨骨折となる場合があります。
交通事故による胸部外傷で最も多いのも肋骨骨折です。
肋骨骨折の症状としては、痛みや圧痛、皮下出血や腫れが生じることがあります。
また、身体を反らす、荷物を持ち上げる、深呼吸や咳・くしゃみの際に痛みを感じることがあります。完治しない場合、変形障害と神経障害が残る可能性があります。
なお、肋骨骨折は、深く折れて内臓に刺さった、というような事態にならない限りは、症状も軽微であることが一般的です。
人の肋骨は12対(24本)あり、それぞれ支え合っているため、そのうちの1本が折れた程度では大きな負担とならないことが多いのです。
肋骨骨折の程度が軽微であるときには、痛み止めや湿布薬を処方した上で経過観察とすることが少なくありません。
痛みがやや強いときには、バストバンドなどで圧迫固定をする保存治療が選択されます。
手術適合となるのは、何本も深く折れているケースなどのごく限られたケースのみです。
(2) 骨盤骨折
骨盤輪は数多くの部位から構成され、体重を支えたり、骨盤内臓器を保護する役割を担っていたりする非常に重要な部位です。
骨盤骨折の原因の大半は、交通事故などによる大きな外的衝撃によるものです。
折れてしまった部位によって、骨盤輪骨折(=骨盤の環状構造の破綻)、寛骨臼(かんこつきゅう)骨折(=股関節の関節面を形成する部位の骨折)などの診断となります。
胸骨骨折の症状としては、疼痛、局所圧痛、腫れなどがあります。
症状が重篤なケースでは、骨盤が保護している内臓器にも影響が及ぶことで排泄障害などが残ることもあります。よって、骨盤周囲の血管や膀胱・直腸・尿道などに損傷がないかきちんと検査する必要があります。
交通事故における骨盤骨折は、頸椎損傷、胸部外傷について重篤なケースであると認知されています。大量に出血することも多く、出血と痛みでショック状態になることもあります。
深刻な後遺症が残るケースも多く、骨盤を骨折したことが原因で股関節が健康なときと比べて十分に曲がらない「可動域制限」が残ってしまう、骨折部分が変形して癒合してしまう、骨折部位の癒合後も痛みが残ってしまう、などが考えられます。
骨盤輪骨折の治療は、破綻の程度に応じて選択する方法が異なります。
症状が軽いケースでは、骨折部を外固定することで保存治療を行います。
破綻の程度が中程度(部分不安定型骨折)のときには、2週間程度ベッド上での安静の後に、車いす、松葉杖歩行と段階的に対応していきます。
骨盤輪の後方部が完全に破綻しているケース(完全不安定型骨折)では、手術適合となります。この場合にはプレートなどで骨折部位を固定する処置がなされます。
外固定により筋力が低下した場合には、それを回復させるリハビリも重要でしょう。
2.肋骨骨折、骨盤骨折の後遺障害認定と慰謝料
肋骨骨折や骨盤骨折となったときには、どのような後遺障害が残る可能性があるのでしょうか。慰謝料相場とあわせて確認していきます。
(1) 肋骨骨折の後遺障害
肋骨骨折のときには、変形障害と神経障害が残る可能性があります。
折れた肋骨が変形して接合してしまったときには、変形障害として12級5号の障害認定を受けることができます。
ただし、12級5号の後遺障害等級の認定には、「外見として明確に視認できる程度の変形」がなければなりません。つまり、レントゲンを撮らなければ変形はわからないというときには、変形障害の認定を受けられないということです。
なお、12級5号の慰謝料額は290万円が相場とされています(弁護士基準の場合)。
また、治療終業後も骨折部位に痛みが残る場合には、神経障害として12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)もしくは、14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けられる場合があります。
この場合の慰謝料額の相場は、12級は290万円、14級は110万円です(弁護士基準の場合)。
(2) 骨盤骨折の後遺障害
骨盤を骨折したときには、重篤な後遺症が残ってしまう場合もあります。
①股関節の可動域制限
骨盤を骨折したことが原因で股関節が健康なときと比べて十分に曲がらなくなる「可動域制限」が残ってしまうことがあります。
股関節の可動域制限は、その程度によって次のように障害等級の認定が異なります。
| 後遺障害の状態 | 後遺障害認定等級 |
|---|---|
| 股関節の完全弛緩性マヒ(力が全く入らない状態) | 8級7号 |
| 人工関節などに置換した場合で機能に著しい障害を残したとき | |
| 人工関節などに置換した場合 | 10級11号 |
| 股関節の機能に著しい障害を残す場合 | |
| 股関節の機能に障害を残す場合 | 12級7号 |
「著しい障害」とは障害のない側と比べて可動が1/2以上に制限された状態、「障害を残す場合」とは障害のない側との比較で可動が3/4以上に制限された場合をいいます。
なお、この可動の程度は、医師などの他人の力で曲げられる限界で判定されます。
②骨盤の変形
他の骨の骨折の場合と同様に、骨折部分が変形して癒合したときには12級5号が認定されます。
12級5号の認定には外見上明らかな変形であることが必要なのも、肋骨骨折の場合と同様です。
また、寛骨臼や尾骨の骨折や股関節の脱臼骨折となったときには、下肢の短縮が残る場合があります。
下肢短縮が残ったときには、その程度に応じて後遺障害等級が認定されます。
| 下肢短縮の程度 | 後遺障害等級 |
|---|---|
| 1下肢の5センチメートル以上の短縮 | 8級5号 |
| 1下肢の3センチメートル以上の短縮 | 10級8号 |
| 1下肢の1センチメートル以上の短縮 | 13級8号 |
さらに、女性が骨盤を骨折したときには、変形により産道が狭まり正常分娩が困難となることがあります。その場合には、11級10号が認定されます。
③神経障害(痛みの残存)
骨折部位の癒合後も痛みが残るときには、その状況に応じて、次のとおりの認定と受けることができます。
- レントゲンやMRIなどの画像診断で痛みの原因が確認できる場合には12級13号
- レントゲンやMRIなどの画像診断で痛みの原因が確認できない場合には14級9号
④骨盤骨折の後遺障害慰謝料
骨盤を骨折したときの後遺障害に対する慰謝料の相場額は、次の通りです(弁護士基準の場合)。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準での慰謝料額 | 自賠責基準での慰謝料額 |
|---|---|---|
| 8級 | 830万円 | 327万円 |
| 10級 | 550万円 | 187万円 |
| 11級 | 500万円 | 135万円 |
| 12級 | 290万円 | 93万円 |
| 13級 | 180万円 | 57万円 |
| 14級 | 110万円 | 32万円 |
3.弁護士に示談交渉を依頼することのメリット
交通事故の被害に遭い骨折などの受傷をした時、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 相手方保険会社との交渉を任せられる
- 十分な治療を受けることに専念できる(適切な検査を受けられる)
- 適切な後遺障害等級の認定を受けられる
- 十分な損害賠償額を受け取ることができる
(1) 相手方保険会社との交渉を任せられる
交通事故の被害者となった場合、大抵は相手方(加害者側)の任意保険会社と賠償金=示談金について交渉することになります。
しかし、相手は交通事故に関する示談交渉のプロです。交通事故被害者が単独で保険会社と対等に交渉を進めることは難しい場合があるでしょう。
「過去の事例ではこのくらいの金額です」「その症状は交通事故が原因ではないのでは?」などと言われ、不当に示談金を減らされてしまう事例は少なくありません。
また、受傷による痛みが続く中、通院・治療をしながら自ら示談交渉を行うことはかなり辛い作業であるともいえます。
そんな中、弁護士に示談交渉の代理人をお願いすれば、相手方保険会社の理不尽な主張を退け、対等あるいは被害者側に有利なペースで示談交渉を進めることができます。
(2) 十分な治療を受けることに専念できる
上記から繋がりますが、弁護士に示談交渉を任せることで、被害者の方は怪我の治療に専念することができます。
さらに、保険会社より早期の治療打ち切り(症状固定)を求められたとき*にも、弁護士がいれば保険会社に対して治療継続の必要性などを訴えることでき、十分な治療を受ける機会を確保できる可能性が高くなります。
*通院期間が長くなると、慰謝料をはじめとする賠償額が高額になります。任意保険会社はあくまでも営利団体なので、賠償額を出来るだけ低く抑えようと、一般的に治療が終了すると思われる時期に治療の打ち切りを通告して治療費の支払いをストップするのです(一般的に、骨折は6ヶ月程度と言われています)。
(3) 適切な後遺障害等級の認定を受けられる
後遺障害が残ってしまったときには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが何よりも重要です。
前の段落で説明した通り、あなたの後遺症がどの後遺障害等級に当てはまるかで、慰謝料額は大きく変動します。
後遺障害の認定を受けるための申請は、相手方保険会社にお任せする(後遺障害診断書のみを被害者側で取得し、その他の必要書類は加害者側保険会社が収集した上で自賠責保険に申請する)「事前認定」と、被害者自身が書類などを揃えて申請する「被害者請求」があります。
被害者請求は、自分で書類収集を行うので、認定に向け有利な証拠や書面を積極的に集めて提出できるというメリットがありますが、その分手間がかかるというデメリットもあります。
一方、事前認定は自分で集める書類は後遺障害診断書のみで済むので手間は省けますが、加害者側の任意保険会社に書類収集を委ねることになるので、熱心な証拠や書面の収集が期待しにくくなります。書面を十分に集めてもらえなければ、実際の症状よりも低い等級で認定されてしまうリスクがあります。
弁護士にサポートを依頼すれば、被害者請求の書類収集や提出までを一括してサポートしてくれます。
自力での被害者請求は困難であるため、適切な後遺障害認定を受けたいならば弁護士に依頼するのが最適でしょう。
(4) 十分な損害賠償額を受け取ることができる
交通事故の損害賠償項目の中には「慰謝料」というものがあります。
慰謝料とは、交通事故により、怪我や通院、入院等を余儀なくされたことの精神的苦痛に対する賠償金です。
特に、治療を続けても完治せず、後遺症が残ると就業能力にも問題が発生するため、傷害部分とは別に後遺障害としてその精神的苦痛を賠償することが認められています。これを後遺障害慰謝料といいます。
交通事故の慰謝料の算出基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。
自賠責基準による算定が最も賠償金が安く、弁護士基準が最も高額な算定となります。
弁護士が介入しない示談交渉で弁護士基準による損害賠償額が提示されることはまずありません。弁護士基準は、弁護士が介入することで裁判になることを恐れた相手方保険会社が、裁判を回避するために賠償金を引き上げた結果適用される基準なのです。
特に、後遺障害が残るケースでは、弁護士基準とそれ以外の基準とで受け取れる補償額が倍以上異なることも多くあります。
保険会社から提示された慰謝料額などに不満があるときには、弁護士にご相談ください。
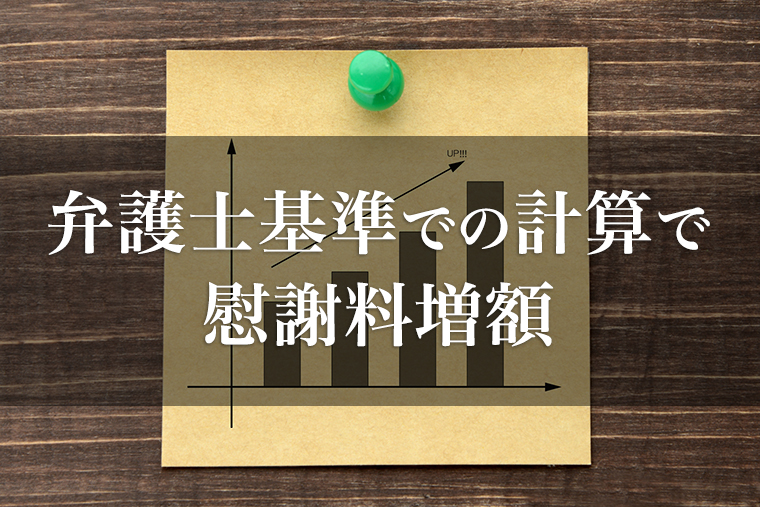
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
4.まとめ
交通事故で肋骨や骨盤にダメージを受けたときには、特に後遺症に配慮する必要があります。
後遺障害が残ることが疑われるケースでは、症状固定前の治療段階から交通事故の実績が豊富な弁護士によるサポートを受けることが非常に大切です。
弁護士にご依頼いただくことで、通院・治療に関するアドバイス、治療費打ち切りへの対応、適切な後遺障害等級の認定などが受けられます。結果、十分な補償を確保でき、怪我の治療やリハビリに安心して専念することができます。
治療期間中の交渉経緯などから保険会社の対応に心配があるときには、早めに弁護士にご相談・ご依頼いただいた方が良いでしょう。
お困りの時には、些細なお悩みであっても泉総合法律事務所までご相談いただけたらと思います。