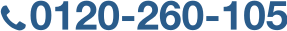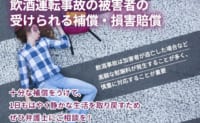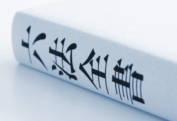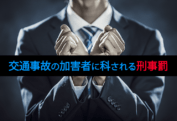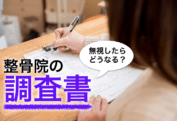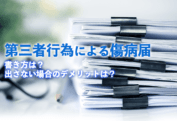人身事故(交通事故)の刑事責任・民事責任・行政責任の違いとは

人身事故とは、被害者の生命や身体を傷つけてしまう形態の交通事故です。
人身事故を起こした場合、加害者は民事責任、刑事責任、行政責任の3種類の責任を負います。
今回は、それぞれの責任の内容や違いについて解説します。
交通事故被害者の方が読んでも参考になる内容を盛り込んでいますので、ぜひご一読ください。
1.交通事故の民事責任とは
人身事故の「民事責任」とは、被害者に生じた生命・身体に関する損害を金銭的に賠償する責任です。
より具体的には、不法行為責任と運行供用者責任の2つを理由として賠償責任を負います。
(1) 不法行為責任
まず、自動車の運転上必要となる注意を怠り他人にケガを負わせた場合は、不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償義務を負います。
もちろん、怪我人のいない物損事故の場合でも、加害者は被害者の車両の修理費等の物損について賠償する責任を負います。
しかし、人身事故の場合、より重要になるのは人損、すなわち被害者の生命・身体に関する損害の賠償です。
人損は、傷害による損害と後遺障害による損害に区別されます。
傷害による損害とは、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの主として事故によるケガの治療中に発生する損害です。
他方、後遺障害による損害は、治療終了時において残存した後遺障害により生じる将来に渡る損害であり、基本的には、後遺障害慰謝料と逸失利益になります。
逸失利益とは、後遺障害の存在により将来的に得られるはずの労働による収入を得られなくなったことについての損害のことです。
交通事故の加害者は、これらの損害を賠償する金銭を支払う責任が生じるのです。
(2) 運行供用者責任
次に、人身事故を起こした加害者は、加害車両の保有者として運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)を負います。
運行供用者責任は、不法行為責任とは違い人損の賠償責任に限定されたものです(物損は対象外です)。
運行供用者責任は「①加害者の無過失」「②被害者又は第三者の故意又は過失」「③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害のなかったこと」の3点を証明しない限り、その責任を負うことになります。その意味では、不法行為責任より重い責任です。
人身事故の加害者は不法行為責任と運行供用者責任の双方を同時に負うことがあります。しかし、そのことにより被害者は賠償金を二重に取得できるわけではありません。
たとえば、人損の賠償額が200万円の場合、加害者は200万円の賠償金を支払うことにより、不法行為責任と運行供用者責任の双方を果たしたことになります。
2.交通事故の刑事責任とは
よく、人身事故を起こした加害者から「今示談金を払うので、警察への事故の届出を控えてほしい」と要請されることがあります。
その理由の1つは、警察に届けられ人身事故の扱いになると刑事責任に問われる可能性があるからです。
人身事故の刑事責任は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)や道路交通法(道交法)などに定めがあります。
以下、人身事故が具体的にどのような罪に当たり、どのような刑罰に処せられるのかについて説明します(別途一覧表参照)。
なお、日本では起訴裁量主義といい、罪を犯した者でも検察官の裁量により起訴しない(すなわち刑事罰を科さない)と判断されることがあります。
人身事故の場合でも、被害者との示談の成立状況、被害者の処罰感情など処罰の必要性、その他の諸事情を考慮して起訴されないことがあります。人身事故を起こせば常に刑事責任に問われるわけではありません。
(1) 過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させる行為は、過失運転致死傷罪に当たり、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金に処せられます(自動車運転処罰法5条)。
一般的な人身事故のケースであれば、多くがこの過失運転致死傷罪の適用対象になるでしょう。
(2) 危険運転致死傷罪
飲酒運転等の危険運転による人身事故については、危険運転致死傷罪として、過失運転致死傷罪より重く処罰されます(自動車運転処罰法2条・3条)。
危険運転に当たる行為は法律で定められています。具体的には、飲酒・薬物の影響により正常な運転の困難な状態での自動車の走行、信号を無視した高速度の自動車の走行などです。
危険運転致死傷罪に当たる場合、人を負傷させた場合は15年以下(下限は原則1ヵ月)の懲役、人を死亡させた場合には1年以上(上限は原則20年)の懲役に処せられます。
また、飲酒・薬物・病気(政令により指定された自動車の運転に支障の生じさせるおそれのある病気)の影響により走行中に正常な運転に支障の生じるおそれのある状態で自動車を運転して、実際、正常な運転に支障が生じて人を死傷させた場合にも危険運転致死傷罪になります。
この場合には、人を負傷させた場合は12年以下(下限は原則1ヵ月)の懲役、人を死亡させた場合には15年以下(下限は原則1ヵ月)の懲役に処せられます。
(3) 無免許・飲酒等の影響の発覚を免れる行為・ひき逃げによる罪の加重
その他、単に人身事故を起こしただけでなく、無免許運転(自動車運転処罰法6条)、飲酒・薬物の影響の有無・程度の発覚を免れる行為(自動車運転処罰法4条)、ひき逃げ(道路交通法72条)については、更に重い刑事責任を科せられます。
| 罪名 | 行為 | 法定刑 | |
|---|---|---|---|
| 負傷 | 死亡 | ||
| 過失運転致死傷罪 | 自動車の運転上必要な注意を怠る行為 | 7年以下(下限1ヵ月)の懲役または100万円以下(下限1万円)の罰金 ※無免許:10年以下の懲役 ※負傷の程度の軽いときは刑の免除の可能性 |
|
| 危険運転致死傷罪 | アルコール・薬物の影響により正常運転困難の状態での走行 | 15年以下(下限1ヵ月)の懲役 ※無免許:6ヵ月以上(上限20年)の懲役 1年以上(上限20年)の懲役 |
1年以上(上限20年)の懲役 |
| 進行制御困難の高速度の走行 | |||
| 進行制御の技能欠如での走行 | 15年以下(下限1ヵ月)の懲役 | ||
| 人・車の通行の妨害を目的に重大な交通の危険を生じさせる速度での割り込み、過剰接近運転 | 15年以下(下限1ヵ月)の懲役※無免許:6ヵ月以上(上限20年)の懲役 | ||
| 赤信号(類似信号)を殊更に無視して重大な交通の危険を生じさせる速度での運転 | |||
| 通行禁止道路の重大な交通の危険を生じさせる速度での運転 | |||
| アルコール・薬物・政令指定の病気の影響により、正常運転に支障の生じるおそれのある状態での運転 | 12年以下(下限1ヵ月)の懲役 ※無免許の場合:15年以下の懲役 ※アルコール・薬物の影響の有無・程度の発覚を免れる行為をした場合は12年以下(下限1ヵ月)の懲役 |
15年以下(下限1ヵ月)の懲役 ※無免許:6ヵ月以上(上限20年)の懲役 ※アルコール・薬物の影響の有無・程度の発覚を免れる行為をした場合は12年以下(下限1ヵ月)の懲役 |
|
3.交通事故の行政責任とは
人身事故を起こした場合、自動車運転免許の点数制度において加点され、累積の点数に応じ免許停止・免許取消になることがあります。
自動車運転免許制度は公安委員会という行政機関の管轄のため、こうした免許停止・免許取消に関する責任は「行政責任」といいます。
人身事故による点数加算は以下のようになります。
- 人身事故を起こしたこと自体により2点
- 事故により生じた結果と加害者の不注意の程度に応じて2点~20点加算
- ひき逃げの場合には更に35点加算
行政処分歴のない人の場合、6点~14点の場合には免許停止、15点以上の場合には免許取消になります。
なお、点数の計算は原則として事故日から遡って3年間の累積計算です。
点数加算に関しても、下記に一覧を用意しました。気になる方は参考にしてみてください。
| 内容 | 加害者の一方的過失 | 被害者に過失あり | ||
|---|---|---|---|---|
| 安全義務違反 | 2点 | |||
| 死亡事故 | 20点 | 13点 | ||
| 負傷 事故 |
重傷 事故 |
治療期間3ヵ月以上・後遺障害 | 13点 | 9点 |
| 治療期間30日以上3ヵ月未満 | 9点 | 6点 | ||
| 軽傷 事故 |
治療期間15日以上30日未満 | 6点 | 4点 | |
| 治療期間15日未満・建造物損壊事故 | 3点 | 2点 | ||
| ひき逃げ | 35点 | |||
4.まとめ
人身事故を起こした場合には、民事責任、刑事責任、行政責任の3つの責任を負い、いずれも重大な責任です。
民事責任は、被害者に生じた損害の補填を目的とするものであり金銭による賠償責任です。
刑事責任は、犯罪の一般的抑止を目的とするものであり、昨今、特に態様の悪質な人身事故についての厳罰化の傾向にあります。
行政責任は、自動車運転免許制度における免許停止・免許取消に関する責任です。重大な人身事故を起こしたり、人身事故を繰り返すような運転者が自動車に乗らないようにすることを目的としています。
泉総合法律事務所では、交通事故の被害者となってしまった方のご相談を、お電話とメールにて受け付けています。交通事故問題に強い専門の弁護士が、事案に応じてしっかりサポートいたしますので、お困りごとがあれば是非ご相談ください。
他方、交通事故加害者となってしまった方としては、それぞれの責任を前に不安になることかと思います。交通事故加害者となってしまった方は、下記ページをご参照ください。
交通事故加害者の方のご相談について