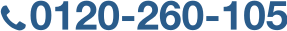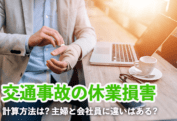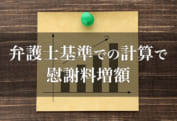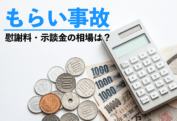後遺障害を負った専業主婦・主夫は賠償金・慰謝料をいくらもらえる?

交通事故によって後遺障害が残ったときには、後遺障害慰謝料・逸失利益の支払いを受けることで損害を補填します。
主婦(主夫)の役割は家庭においてとても重要です。主婦の方が後遺障害の残る交通事故被害に遭ったときには、家事などに大きな支障がでることが少なくありません。
しかし、相手方の保険会社は、「専業主婦は収入がなく、後遺障害による支障も少ないだろう」などと言って、支払う損害賠償を非常に低く見積もってくるケースが多々あります。
後遺障害を残すほどの交通事故は、ほとんどの被害者がはじめての体験ですので、保険会社にこう言われて鵜呑みにしてしまうケースも実は少なくありません。
しかし、大事なのは相手方の保険会社のペースで示談に応じず、主婦が交通事故で後遺障害を負ったときの損害賠償がどうなるかを理解した上で適切に反論して正当な金額の賠償金を受け取ることです。
この記事では、主婦(主夫)が交通事故で後遺障害を負ってしまった場合の賠償金(慰謝料)について解説していきます。
1.後遺障害が残ったときの主婦の慰謝料
まず、後遺障害が残ったときには、それによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料(=後遺障害慰謝料)が認められます。
精神的な苦痛を金銭評価することは簡単ではない(立証責任は被害者にある)ので、日本においては、後遺障害の程度に応じて一律に賠償額を算出する実務が採用されています。
たとえば、自賠責保険における後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて下の表のようになります(※裁判となった場合に裁判所が認める基準)。
| 第1級 | 2,800万円 | 第8級 | 830万円 |
|---|---|---|---|
| 第2級 | 2,370万円 | 第9級 | 690万円 |
| 第3級 | 1,990万円 | 第10級 | 550万円 |
| 第4級 | 1,670万円 | 第11級 | 420万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 第12級 | 290万円 |
| 第6級 | 1,180万円 | 第13級 | 180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 第14級 | 110万円 |
保険会社が被害者本人と示談交渉をする場合、上記よりもかなり低い金額で見積もられた慰謝料の金額が算出・提示されることがほとんどです。
そんな時は、示談交渉を弁護士に依頼すればほとんどのケースで上記の金額に近いところまで慰謝料の増額が期待できます。
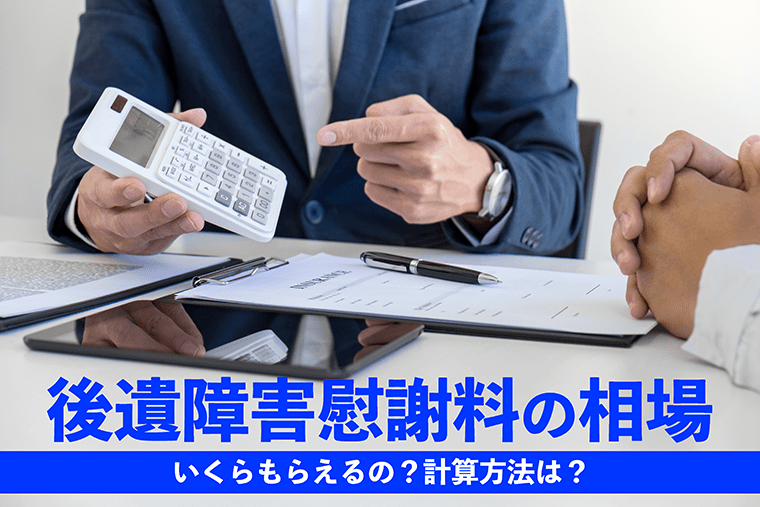
[参考記事]
交通事故の後遺障害慰謝料の相場はいくら?
もちろん、「主婦だから慰謝料の額が少なくなる」ということはありません。
後遺障害が残ったことによる生活上の不便さや精神的苦痛は、「フルタイムで働いている人」「兼業主婦」「専業主婦」の違いで変わることはないからです。
一方で、認定された後遺障害等級の程度を超える精神的苦痛が認められる特段の事情があるときには、基準額を超える慰謝料が認められる場合もあります。
たとえば、主婦(女性)が後遺障害を負った場合に、慰謝料が増額される特段の事情の例としては、次のものが挙げられます。
- 後遺障害によって離婚を余儀なくされた場合
- 後遺障害によって退職や廃業を迫られた場合
- 後遺障害によって家族の負担が増加した場合
- 後遺障害が原因で流産・中絶した場合
- 交通事故の態様が悪質なものであった場合(飲酒運転・ひき逃げなど)
また、主婦が交通事故によって重度の後遺障害を負ったときには、家事などについての家族の負担が著しく増大する場合も少なくありません。
このような場合には、被害者本人の慰謝料に加え、主婦が担っていた家事を負担することになった夫や子などに「独自の慰謝料」が認められる場合もあります。
2.後遺障害が残ったときの主婦の逸失利益
交通事故による後遺障害によって就業などに影響が生じ減収となったときには、「逸失利益(いっしつりえき)」の補償を受けることができます。
逸失利益は、後遺障害によって減収となった場合のほか、死亡事故に遭って将来の収入が断たれたときにも補償を受けることができます。
交通事故の損害賠償実務において、逸失利益は次の計算式で算出されます。
「逸失利益」=「基礎収入」×「後遺障害による労働能力喪失率」×「ライプニッツ係数」
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級ごとに定められている係数を用います。
ライプニッツ係数は、中間利息を控除するための指数です。逸失利益は、将来に向かって発生する損害賠償を現在の時点でまとめて受け取るため、中間利息を控除する必要があります。
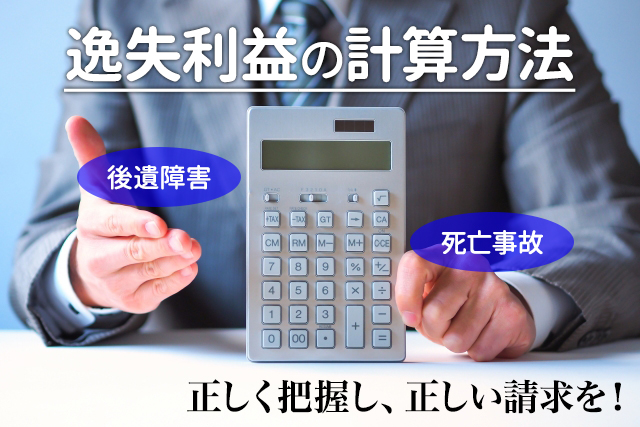
[参考記事]
後遺障害・死亡事故の逸失利益の計算例|もらえない原因を解説
さて、逸失利益の算出根拠に「基礎収入」が含まれるため、「収入のない専業主婦には逸失利益は発生しない」と勘違いしている人が少なくありません。
しかし、実際の損害賠償請求の場面では、専業主婦であっても逸失利益を請求することができます。主婦の家事労働は金銭評価されるべきものだからです。このことは、最高裁の判例でも認められています(最判昭和49年7月19民集28巻5号872頁)。
専業主婦の基礎収入は、自賠責の基準と裁判の基準で用いる指標が異なります。
自賠責基準では、金融庁・国土庁が告示する「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」が定めている全年齢平均給与額の年相当額を用います。
これに対し、裁判基準では、「女性労働者の全年齢の平均賃金(賃金センサス)」を用います。
慰謝料額の場合と同様に、一般的には自賠責基準の方が逸失利益は低く算出されます。よって、逸失利益を増額したいならば弁護士に交渉を依頼するべきと言えます。
なお、週30時間未満の労働をしている兼業主婦の場合には、実際の収入と平均賃金の高い方を基礎収入として用います。
週30時間以上の労働をしている人については、給与所得者の基礎収入が適用されます。
【専業「主夫」の場合は逸失利益が上がる?】
近年では、夫が家事を専業に担当する専業主夫も増えています。たとえば、賃金センサスも自賠責基準が定める平均給与額も女性より男性の方が高額です。そのため、主婦よりも主夫の方が多額の逸失利益をもらえるのではないかと考える人もいるかと思います。
しかし、裁判実務においては、専業主夫の場合でも、女性労働者の平均賃金を用いることが多いので、専業主夫と専業主婦で逸失利益の額が異なることはありません。家事労働の金銭的評価として「女性労働者の平均賃金」が適用されるので、主婦であろうが主夫であろうが基礎収入は同じだと考えるべきだからです。
ただし、自賠責基準は、機械的に性別に基づいて基礎収入が算出されるため、主夫の逸失利益の方が主婦の逸失利益よりも高額となる可能性があります。
3.まとめ
交通事故の損害賠償請求は、専門的・技術的な要素が多く、一般の方にはわかりづらいことが少なくありません。
また、被害者本人が保険会社と交渉する場合には、知識・経験の差で不利な結果を強いられる場合も少なくないでしょう。
特に、後遺障害が残ってしまった場合には、今後の生活のために十分な補償を確保すべきです。
慰謝料や逸失利益の増額を求めるには、弁護士によるサポートが必要不可欠です。弁護士費用の支払いを不安に感じる人も多いかもしれませんが、後遺障害があるケースでは、弁護士が介入したことで増額される慰謝料額は弁護士費用よりも遙かに多い場合が少なくありません。
交通事故の被害に遭ってお困りの時には、泉総合法律事務所にご相談いただければ、交通事故に特化した弁護士が責任もってサポートさせていただきます。
お気軽に、泉総合法律事務所の弁護士に無料でご相談ください。